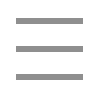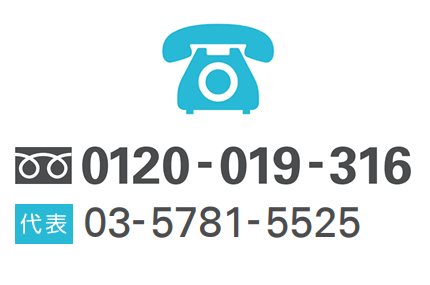代表長尾が語る経営の道標
2ヶ月に一度更新しています
2020年版 経営の道標
無形資産をデジタル化し限界費用ゼロで付加価値を高めよ
菅政権になってデジタル庁が発足することになった。コロナ禍の影響もあるだろうが、今まで遅々として進まなかったハンコレス、ペーパーレスも一気に進もうとしている。リモートワーク、テレワークも当たり前のようになって来た。営業部門はコンタクトレス・アプローチにシフトして行くことになるだろう。
未だにDX(デジタル・トランスフォーメーション)は一般に理解されていないようだが、学校でもデジタル教育が始まりオンライン授業も増えるだろうから、2021年は日本企業のデジタル化元年、デジタル改革スタートの年となるのではないか。そうなって欲しいと思う。
だが、企業の現場、経営者の動きを見ていると、DXなど程遠い、単なるIT化によるコストダウン程度の話で終わる企業が少なくないのではないかと危惧している。デジタル化とは何か、デジタル化することで何を得ようとするのかという議論もなく、単にハンコをなくし紙をなくしたところで、大した成果にはならない。そこに補助金をどれだけ注ぎ込もうとも、ITツールの導入は進んでも、デジタル化による企業の変革をもたらすことにはつながらないだろう。
そこで、コロナ騒ぎで終わりそうな2020年の最後に、2021年に向けた「経営の道標」を書いておきたい。
・コストダウン効果はかかっているコスト以上に出ることはない
まず多くの企業で、IT化、デジタル化する際の効果をコストダウンに求めてしまうという問題がある。ハンコレス、ペーパーレスにしたら今までかかっていたコストが半減できます、いくらになります、〇〇〇円の効果が期待できます、と考える。コスト削減は効果を数値で表しやすいから、ITベンダーの提案も社内の説得も簡単だ。IT化のコストとコストダウン効果を比較すれば、ITに疎くても一目瞭然で意思決定できる。
しかし、コストダウン効果は、かかっているコスト以上に出ることはない。たとえば、請求書をペーパーレス化してWEB配信に切り替えたら、それまで月に3万円かかっていた請求書を発行し郵送するコストが、1万5千円に半減できる。これはこれで素晴らしいことだ。しかし、それでは年額にしても18万円の効果しかない。これが中堅・中小企業の「IT化あるある」だ。要するにかかっているコストがそもそも小さいから、やらないよりやった方がいい程度の話になってしまう。コストが仮にゼロになったとしても36万円の効果しかない。
これが大企業なら、ある業務に36億円かかっていて、それが半減できれば18億円の利益改善ができる・・・といった桁違いの話になる。年に18万円なら誤差みたいな話だが、18億円ならそこそこの規模の会社でも一定の成果と見做されるだろう。桁を落として、3億6千万が1億8千万になってもまずまずの業績改善効果だ。しかし、中堅中小ではそれだけのコストをかけている業務がそもそもなかったりするわけだ。
もちろん、コストダウン効果を否定したいわけではない。額が小さかったとしても、確実に成果が見込めるから、取り組みやすいものであり、やらないよりはやった方がいいに決まっている。現実には、こうした確実に成果が見込めるIT化投資であっても二の足を踏むような企業、経営者も多いから、IT化すら進まないわけだが・・・。
・デジタル化は売上アップにつなげてこそ大きな効果がある
コストダウンも大事だが、デジタル化は売上アップ、付加価値アップ、顧客価値アップにつなげてこそ本来の力を発揮するということを企業経営者にはしっかりと理解していただきたい。
自社の販売プロセスや顧客サポートプロセスをデジタル化し、顧客対応力を上げ顧客満足度を高め、顧客が認める自社の価値を高めることを考えよう。もしくは、自社の商品にデジタル要素を組み込んで商品価値を高めることを考えてみる。簡単な例で言えば、自社の商品パッケージにQRコードをつけてそこからリンクした先に、商品の製造プロセスや素材のトレース情報を開示したり、利用方法・調理方法などの情報を継続的に提供するような仕組みを考えるといったことだ。
こうした取り組みは、初期導入時、開発時にはコストがかかるが、一度出来上がれば、あとは限界費用ゼロで利用することができる。客数や件数がいくら増えても追加費用がかからないということだ。すると、客数や件数が増えれば増えるほど付加価値が増えて行くことになる。必ず成果が出るという保証はないが、成果が無限に広がる可能性がある。
デジタル化が持つ、この限界費用ゼロという特性を最大限に活かしてこそデジタル化の意味があるのだ。デジタル化によってコストダウンができるのも、この限界費用ゼロという特性のおかげなのだが、せっかく限界費用がゼロなのに、コストがかかっている範囲でしか利用しないから、効果が限定的になるわけだ。
だが、これを売上アップ、客数アップに使えば、効果は無限に広がる。この時に、効果があるかどうか分からない、成果につながるかどうか不確定要素が多い、と躊躇していてはデジタル時代を生き抜くことはできないだろう。米中のIT巨人に飲み込まれるか、吹き飛ばされて終わり、となる。
米国企業は創業時からグローバル展開を考えていて少なくとも英語圏の人口を狙っている。中国企業は中国国内だけで14億人のマーケットがある。それに対して日本企業は全国で戦うとしても日本語が通じる1億ちょっとを相手にビジネスを考えている。この時点で、日米、日中の企業間には生産性の差が生じて当然なのだ。ここでは国際比較がしたいわけではないので、この話は置いておこう。
売上や客数の拡大余地によってデジタル化の恩恵にかなりの差があるのだが、日本語の壁に守られた中で客数が増やせるかどうかと悩んで躊躇しているようではお話にならない。デジタル化は売上アップにつなげることを意図してこそ、その価値を活かせるものだとしっかり認識してもらいたい。
・無形資産をデジタル化することでスケーラビリティが高まる
限界費用がゼロ、すなわち変動費が非常に小さいということと同時に、考えておくべきなのが無形資産のスケーラビリティを活用することである。
無形資産とは、ソフトウェア・ノウハウ・特許・デザイン・商標・知識・技能・ブランド・ビジネスモデル・顧客データなどを指し、会計的に把握されていないか、されていても資産計上されておらず取得時の経費として処理されている「形の無い(会計上の数値で表されていない)」資産のことである。例外は、企業買収時に発生する、簿価と買収価格との差「のれん代」だが、この「のれん代」も無形資産の価値を正しく表現しているとは言えない。
従来の投資の対象は固定資産だった。土地や建物や機械、設備などの形あるものだ。固定資産も企業の収益性を高める。好立地の土地や建物は収益を生むし、優秀な機械や設備も稼働すればするだけ収益を生み出す。だが、固定資産の場合、ある土地はその場所にしかないし、ある土地に建物を建てればそこに他の建物は建たない。工場に機械を設置する際に、台数を増やそうとしても限界がある。一台の機械が生み出す製品数量には限界があり、一日24時間一年365日フル稼働しても生産量はどこかで頭打ちになる。
一方、無形資産は、形が無いのだから複製し、何度も何度も再利用し、世界中に拡散させても送料がかからず摩耗もしない。複製回数も利用回数も制限がなく、拡散エリアの制約もない。これが無形資産のスケーラビリティだ。
但し、この時、無形資産を複製したり再利用したり拡散させる媒体をデジタル(データ・IT)にしなければならない。知識やノウハウを「本」という形にしたら有形資産になって送料や保管料がかかる。また、無形資産を人間を媒介にして拡散すれば、限界費用はゼロのままだが、24時間365日という時間の制約を受けてスケーラビリティが小さくなる。だが、デジタルが媒介すれば、時間的物理的な制約を超えスケーラビリティが飛躍的に高まる。
このデジタル化によるスケーラビリティが、固定費を雲散霧消させて、会計上も限界費用がゼロと言える状態にしてくれる。実質的には限界費用はゼロなのに、初期費用、開発費用が配賦されて会計的な原価計算上は売上原価がついて回っているからだ。だが、仮に10億円の固定費(資産の償却を含む)がかかっていたとしても10億件の客数で分担すれば、1件当たりの原価は1円となって、ほぼ無視して良くなる。ここで、もう一度、「デジタル化は売上アップにつなげてこそ大きな効果がある」という話に戻る。デジタル化によって無形資産のスケーラビリティを活かしたいのに、コストダウンのような限定的なことを対象にしてはスケーラビリティが活かせないからだ。
そこで大切になるのが、自社独自の無形資産をデジタル化するということ。単にどこにでもあるITツールを持って来て社内業務をデジタル化しただけでは、他社との差別化も出来ず、効率が上がってコストは下がっても売上増、客数増につなげられないからだ。要するに、デジタル活用とはITだけの問題ではないということだ。自社ならではの知識や技能があり、それが特許や商標などで法的に保護もされて、優れたデザイン性を伴ってブランド化できていて、独自のビジネスモデルに載せて拡販(スケール)するデジタル化、IT活用を目指さなければならない。
GoogleやFacebook、Microsoftをイメージしてみれば分かりやすいだろう。いきなりGoogleやFacebookと戦おうと思っても勝ち目はないから、GAFAMに対抗する必要はないが、彼らがどういうカラクリで利益を創出しているのかは理解しておかなければならない。デジタル化とは、IT導入やIT化ではなく、すべての企業がデジタル企業になることを指す。今や、Amazonが本を売っているからと言って、本屋だと思っている人はいないだろう。だが、元々は本屋だった。ネットで本を売っていたに過ぎなかったし、他にも同様なネット書店はあった。
・無形資産を生み出すのは「人」である
無形資産をデジタル化し売上アップにつなげることでスケーラビリティが活かせるようになるという話をして来た。デジタル化とはその仕組みを企業に組み込むことであり、それをビジネスモデルとして確立させることである。
では、その無形資産が、自社にあるのかどうか、心配になる人がいるだろう。「うちの会社に果たして無形資産と言えるようなものがあるのだろうか」と。無形だから見えにくいが、企業として成り立っていれば無形資産はゼロではない。少ないかもしれないが、新たに作って行くこともできる。生み出し、投資し、蓄積して行けば良いのだ。
無形資産とは、ソフトウェア・ノウハウ・特許・デザイン・商標・知識・技能・ブランド・ビジネスモデル・顧客データなどを指すと上述した。これらがまったくない企業はないだろう。これらに磨きをかけ、新たな価値を生み出して行くことを考えなければならない。
その無形資産は、「人」が生み出す。必ずしも社員である必要はなく、外部の「人」であっても良いが、「人」の頭脳が生み出す。価値はプライスレスだ。金額(数値)で表せないから会計的に処理できない。仕方がないので、「人」が動いた時間の人件費(外部の場合は外注費)で金額を出し、ソフトウェアなどの一部は資産計上されているが、多くの場合、資産計上せずに経費で処理している(研究開発費は無形資産を生み出す最たる取り組みだが、経費である)。お分かりと思うが、この場合の会計数値にほぼ意味はない。同じ一時間で時給が同じ「人」がいたとしても、その二人が生み出す無形資産の価値は同じではないからだ。優れたプログラムコードを書く人の一時間とバグだらけのコードしか書けない人の一時間が同じであるわけはないが、この差は会計的に金額で表すことができない。プライスレス。
だから、無形資産を積み上げるには、「人」がプライスレスな価値を生み出してくれる経営をしなければならない。そこで、使命感や理念を共有する目的主導型経営が求められる。より価値の高い無形資産を生み出してくれる「人」を集められる企業が勝つ。金のために嫌々時間を過ごそうとする「人」は、時給程度の価値しか生んでくれない。それなら外注で充分であり、その方が環境の変化にも強い。
あなたの会社は、目的主導型の経営ができているだろうか。複製し拡散させたい無形資産が蓄積されているだろうか。それもないのに、デジタル化、IT化を進めるだけで本当に良いのだろうか。
デジタル化元年となるであろう2021年を迎えるにあたり、改めて考えてみていただきたい。
2020年11月
パンデミックをプラスに転じることができるか
Content Is Kingとは、1996年のビル・ゲイツの言葉で、WEBマーケティング界では「結局、最後はContent Is Kingだよね」と言われたら、そこで話は終わり、になってしまうほどのパワーワードだ。Contentとは、直訳すると中身、内容物のことであり、Content Is Kingとは、中身が王様ということになる。
無限に広がるWEB、ネットの世界では、検索して上位に表示されて発見してもらえなければ存在しないに等しい。そこでGoogle様に見つけてもらえるようにSEO(Search Engine Optimization・検索エンジン最適化)対策をしなければならないのだが、仮にSEOに成功して上位表示されたとしても、そのサイトにContent、すなわち中身がなければ意味がないという話。もちろんGoogle様も当然Contentに価値があるかどうかをチェックしているから中身がないことには、そもそも上位表示が難しい。
こうしたことをまだGoogleもなかった1996年に喝破したビル・ゲイツはさすがだな、と感心するしかないが、なぜこんな話をいきなり持ち出して来たかというと、世の中がコロナウイルスの影響で急速にオンライン化、ネット化したことで、ビジネス上にあった物理的な距離や時間などの障壁を取っ払ってしまいつつあるから。
その物理的な壁、限界を超えて新常態(ニューノーマル)に適合した営業活動、顧客アプローチを行う方法論を「
コンタクトレス・アプローチ」と呼んで提唱しているのだが、「
コンタクトレス・アプローチ」を進めて行くと、結局のところ、「自社の価値」「自社が提供できる価値とは何なのか」という自社の中身、Contentが問われることになる。
「
コンタクトレス・アプローチ」によって物理的な障壁がなくなると、これまでリアル訪問するために限定せざるを得なかった商圏を一気に広げることが出来る。これで、地方の企業が全国に打って出ることも容易になると同時に、これまでリアルな障壁に守られていたローカルマーケットに他地区や全国区の企業から攻め込まれることにもなる。そこで問われるのが、「近いから」「ちょくちょく顔を出してくれる」といったメリット以外の価値を自社がどれだけ提供できるのかということだ。これまでは多少イマイチでも、多少商品力が低くても、「近いから」という理由で注文、受注があった。「呼べばすぐ来る」という便利さが商品力にプラスされていた。だが、それが無くなる。無くなりはしなくても相対的にウェイトが下がる。
そこで、自社には価値がある、中身があるということを自社サイト(ホームページ)に記載して広く認知してもらわなければならない。近かろうと遠かろうと関係なし。言語の問題があるので一応日本国内ということにしておくが、もちろん多言語でやれば世界に広がる。
自社サイトの見直しをし、SEOをしようとすると、冒頭のビル・ゲイツの言葉、Content Is Kingに立ち戻る必要が出てくる。サイトのデザインを良くしても、中身がなければ、SEOもうまく行かない。その中身はただ充実していれば良いのではなく、日本一かどうか。少なくとも日本語圏においてその分野で一番価値がある会社・商品かが問われる。その中身があって初めて、それをどう表現するか、どう伝えるかというWEBサイトの問題に当たるべきなのだ。
「
コンタクトレス・アプローチ」を単なるリモート営業、ZOOM等を使った営業手法だと誤解、混同する人が多いのは残念なことだ。コロナウイルス対策のその場凌ぎでWEB会議ツールを使えばいいといった単純な話ではない。そんなことをわざわざNIコンサルティングが本まで出して提言する必要などないではないか。そうではなく、コロナ禍を契機にして営業の在り方、もっと言えばビジネスモデルや組織や人事など経営の在り方も変えて行くべきなのだ。その起点になるのが非接触(コンタクトレス)ということであって、テレワークして、リモート営業していればOKなのではない。
コンタクトレスが常態化することで、物理的な距離や時間を超えられるようになる。そこで問われる自社の「中身」を是非考えていただきたい。貴社に中身はありますか? 日本で一番と胸を張れる商品やサービスがありますか?「近いから」「呼べば来るから」という理由以外で顧客から選ばれている理由は何ですか? この質問の答えを自社サイトに分かりやすく記載すべし。動画も用意し、資料請求したくなる特典資料を用意すると良い。
自社サイトに訴えたいことがない、動画で何を説明したらいいか分からない、特典として渡せる資料もない、という会社および経営者は、ビル・ゲイツの1996年の言葉を改めて胸に刻む必要があるだろう。自社が訴えるべき中身をどうすれば良いか、見当もつかないようなら相談していただきたい。「
コンタクトレス・アプローチ」の取り組みは、そこから始まると言っても良いだろう。オンライン、リモート、コンタクトレスの時代だからこそ、中身が問われる。ただ、ZOOMを使って商談すれば良いのではない。WEBコンテンツを考えるにしても、WEB上の美辞麗句ではなく、自社の価値は何か、自社が日本一と言える領域はどこかを考えよう。
2020年9月
対顧客ペーパーレス3種の神器
そもそも日本企業は生産性が低く、IT化を進めなければならないと指摘されていたところに、コロナウィルス対策でテレワークが必須のように言われ、企業のペーパーレス化(すなわちデジタル化)は急務となっている。情報伝達に紙という媒体を使うから、ITで処理が出来ない。デジタルデータに変換するために、スキャンしたり、入力したりするから時間もかかるし、ミスも生じる。
「IT化して生産性を上げたい」でも、「テレワークでコロナ対策したい」でも、「対面を無くして非接触にしたい」でも、「保管スペースを小さくしたい」でも、理由は何でも良いが、早急にペーパーレス化を進めることをお勧めする。巷で良く言われているDX(デジタル・トランスフォーメーション)を進める、分かりやすい第一歩であるとも言える。DXという略には未だにどうも馴染めないが、デジタルの力で経営を変えるためにも、紙に書かれた情報ではなくデジタルデータになっていることが前提であり、この点についての可否を議論する必要はない。やるしかないのだから。
その時、問題になるのが、顧客に提出する「対顧客ペーパーレス」だ。社内の手続きや業務処理、申請などに使っている紙の書類のペーパーレス化はそもそも自社内の事情であり、自社で決めたルールに過ぎないのだから、要不要の判別をして、必要なものはさっさとペーパーレス化を進めれば良い。
だが、顧客に提出するものは、受け取る顧客が承知してくれないといけない。こちらの都合だけで進めることは出来ない。恐らく官公庁向けの提出書類などはこれから急速にデジタル化が進むだろう。コロナ騒動で、行政批判が高まって「対面、紙、ハンコ」を無くさないわけにはいかなくなるからだ。すぐにコロッと変わることはなくても変わっていくだろう。今の問題は民間の対顧客だ。ここを進めるために必要な3つのペーパーレス化を提案したい。
対顧客ペーパーレス3種の神器--見積書、請求書、名刺
対顧客ペーパーレス化を進めて行く際に、ここは押さえておきたいという3種の神器がある。見積書、請求書、名刺だ。会社案内や商品パンフレットなどは紙ではなく、タブレットで見せたり、ホームページを見せたりすることも簡単だし、それに対して顧客側の了承も必要ない。しかし、見積書は顧客がそれを会社として正式に作ったものとして認めて受け入れてくれなければならない。請求書は顧客が内容を正しいものと認めて処理し入金してくれなければならない。名刺は顧客がその内容を受け取り相手方のデータも交換で返してくれなければならない。
順に見ていこう。
1.見積書
見積書の作成をExcelで行い、営業担当者任せにしている企業が少なくないが、これは即刻止めた方が良い。ITを使っているつもりになっているのかもしれないが、単なる清書マシーンに過ぎず紙の出力や押印が必要となる。客先に提出するにも、対面持ち込み、FAX、スキャンしてメールといったアナログ対応が必要となる。この辺りの手間が面倒だから上司の承認をもらわずに担当者が勝手に客先に提出したり、テレワーク時には「在宅勤務で上司のハンコがもらえないので」と堂々と未承認のものを提出するような企業も見受けられた。コロナの緊急事態で短期的な話なら仕方ないが、ずっとそれではまずいだろう。
こうした企業のために弊社では、見積書作成WEBシステム「Sales Quote Assistant」をご用意している。商品マスタや顧客マスタから選択して作成するのでミスがないし、AI秘書が商品構成の間違いなどを指摘してくれたりするスグレモノだ。もちろん上司の承認もワークフローでもらえて電子押印され、PDF化された見積書はそのままメール出来る。外出先でも家でもどこでも作成、承認、提出が可能になり、データ共有もされる。見積書をベースにした受注の先行管理も可能だ。
見積段階で、データがデジタル化されているから、それがそのまま受注データにもなり、受注登録もラクだしミスがない。デジタルデータは流れて、つながって行くことで業務効率を上げるのだ。
2.請求書
受注データが販売管理システムに流れて来て、売上が立てば、次は請求書の発行だ。ここのペーパーレス化は業務効率化とコストダウンに大きな成果をもたらす。経理部門に聞いてみればすぐに分かるが、請求書の発行、発送は、月末月初に集中しているし、いちいち紙に出して、封入して・・・と面倒だし、受け取って処理する際にも、郵便を確認し、開封し、入力して・・・と面倒な作業が必要となる。わざわざ紙に出して郵送することで、多大な無駄とコストが発生しているのだ。ちなみに、請求書を一通送るには、少なく見積もっても約100円がかかっている。利幅の大きな商売なら良いが薄利でやっていたら案外大きなコストとなる。人間の作業の手間を金額換算したらさらに大きなコストになることはお分かりだろう。
そこで弊社では、請求書WEB配信システム「Sales Billing Assistant」をご用意している。請求書データを読み込んで自動的に請求先にWEB配信してくれる。ここで問題になるのが、顧客の了解をとって経理担当者のメールアドレスをゲットすることだ。そこで営業部門の出番となる。請求書の問題は、経理部門が処理するものだと考えがちだが、実は営業部門の問題なのだ。「Sales Billing Assistant」は営業担当者にメールアドレスを取得できていない先をリストアップして提示したり、口座はあるのに、半年とか一年とか一定期間請求が発生していない休眠状態になっている先をリストアップして教えたりする。この請求書のWEB配信は、コロナウィルスで在宅勤務が取り沙汰されている今こそ進めるチャンスである。WEB配信されれば、自宅にいても請求書を確認できるわけだから顧客側にもメリットがある。経理部門と営業部門が協力して請求書のペーパーレス化、WEB配信を進めるべきである。相手が法人客なら、請求書WEB配信の方法を教えてあげよう。きっと感謝されるはずだ。
3.名刺
ビジネスに名刺は欠かせないもの、常に名刺入れを持ち、名刺を切らすような営業マンは営業失格、という常識も覆されることになるだろう。かつては、紙の名刺はそのまま保管され、名刺の束やホルダーが人脈の証だった。私も駆け出しの頃は名刺ホルダーに名刺が増えて行くのを見て、なんだか仕事が出来るようになった気がしたものだ。
だが、今や、個人情報保護法によって、紙の名刺をそのまま保管しておけない。廃棄しなければならない。情報の交換が済んだら捨ててしまうようなものなら、初めからデータ交換で良いのだ。わざわざ会社名や部署や住所、電話番号などの情報を紙に印刷するコストをかけ、もらった名刺もそのままではデジタル処理が出来ないから手入力するかスキャンしてデータ化しなければならない。紙を媒介・媒体にして情報を交換するのは資源の無駄だし、効率が悪い。そもそもビジネスから対面が減り、商談がコンタクトレスのオンラインで行われるようになって行くと、名刺交換など不可能になる。
そこで弊社では、オンラインID交換「PIエクスチェンジ=PIeX」という新概念を提言している。紙の名刺の存在を前提とした「オンライン名刺交換」ではなく、完全デジタル化によってより効率的にID情報交換を実現するものだ。
PIeXには3つのルートがある。Mail Exchange、QR Exchange、Appli Exchangeの3つだ。
Mail Exchangeは、WEB商談、オンライン商談の前に必ずと言っていいほどやり取りされるメールの署名情報を読み取ってデータベース化するというものだ。メールの署名はほぼ名刺情報と同じだろう。これをお互いがきちんと書いておけば、デジタルデータなのだから、自動的に読み取ることができる。
次に、QR Exchangeだが、WEB商談の時に初めて登場した人物とのPIeXをするために、WEB商談の背景などにQRコードを表示させ、自分のPIデータを相手が読み取れるようにする。紙の名刺サイズに限定されない情報量を伝えることも可能だ。
とはいえ、リアルに対面して商談することもあるだろう。だが、ソーシャルディスタンスを取りたい。相手が触った名刺を受け取るのがイヤだという人もいる可能性がある。そこで、3つ目に、Appli Exchange。スマホのアプリを使って、相手のスマホとBluetoothでつないでPIeXを行う。弊社では、「NI-C-Name」というアプリを無償でご用意している。単体でも使えるし、弊社の「Sales Force Assistant」をご利用の場合には、データを共有して活用することも出来る。特定の名刺管理業者に個人情報を渡すようなこともしなくて済むので安全だし、世界標準規格であるvCard形式にも対応しているから、汎用性も高い。
コロナ禍を逆手にとって対顧客ペーパーレスを進めよう
コロナウィルスの第2波、第3波もあるかもしれないし、冬になればインフルエンザの流行もある。当面、人との接触を避けてコンタクトレスにしたいというニーズは無くならないだろう。その逆境を逆手にとって、ペーパーレス化を進め、デジタル活用で業務効率を上げることを考えるべきである。今なら「コロナもありますし・・・」と言えば顧客も納得してくれるだろう。ちなみに、コストはその方が下がる。やらない選択はないのだ。
2020年7月
コンタクトレス(非接触)アプローチにシフトせよ
3月に、「パンデミックをプラスに転じることができるか」と題して、新型コロナウイルスによるパンデミックをどうプラスに転じるかというストーリーを示せと、この経営の道標に書いた。そこから更に4月に入って、緊急事態宣言が出され、それが全国に広がって、コロナショックによるマイナスはより大きなものになった。5月14日に39県が解除されたものの、自粛要請は残り、東京、大阪の二大都市圏と北海道は緊急事態宣言が継続されたままである。恐らく5月末には一旦解除されるだろうが、3密を避けろ、マスクしろと自粛モードが続いて、経済の回復には時間がかかるだろう。
という、マイナスの状況をプラスに転じる提案をしてみたい。それが、営業の「コンタクトレス(非接触)アプローチ」だ。営業部門は、テレワークにシフトすることは出来ても、従来のスタイルのままでは、客側が訪問を受けてくれなければ思うように活動出来ない。だから、多くの営業マンは在宅勤務という名の「自宅待機」になってしまっている。従来は、客から「来い」「顔を出せ」「フォローしろ」と言われていたのに、今は「来るな」「面談禁止」と言われてしまう。これでは営業マンは電話やメールを送る程度のことしか出来なくなり、営業活動が実質進まない。営業が止まれば、やがて会社も止まる。会社が止まるとはすなわち会社の終焉を意味する。これでは、実際に営業を止められた飲食店、小売店と同様に、いずれ行き詰まることになる。デパートが休業になって営業機能が止まったレナウンはこのコロナで息の根を止められた。業績低迷が続いていたとはいえ、上場企業が行き詰まるのだから、一般の中堅・中小企業も他人事ではないだろう。
そこで、コンタクトレス(非接触)アプローチだ。コンタクトレス・アプローチとは、「顧客へのリアル訪問(コンタクト)を減らして、逆にアプローチ数を増やすことでより大きな成果を上げる一連の営業行為」を言う。感染リスクもあって、顧客に会えないのだから、それを逆手にとってアプローチ数を増やすのだ。
たとえば、一日に3訪問していた営業マンが、コンタクトレス(非接触)アプローチにシフトして、一日5WEB商談したとしよう。仮に一商談のパフォーマンスが非接触のために8割に低下したとしても、0.8×5=4となって、3訪問よりもパフォーマンスが上がる。なぜこんなことに出来るかというと、営業活動における移動時間のウェイトが大きいからだ。自社の営業工数を分析してみるといい。多くの営業マンが3割から5割程度移動している。一日およそ3時間は移動していると考えていい。だから、コンタクトレスで移動を無くせば、それだけ生産性を上げることが出来る。単純な話だ。
コンタクトレス・アプローチにどのようなものがあるかというと、WEB Meeting、WEBサイト、SNS、YouTube、Webinar、葉書道、TEL、Mail、見積書、請求書など、営業プロセスの川上から川下まで非接触で進める多くの手法がある。これらをRCTAというステップに沿って整備して行くのだが、この詳細は長くなるのでまたの機会に譲ろうと思う。
このコンタクトレス・アプローチには4Eという大きなメリットがある。4Eとは、
◇Environment 環境
◇Ecology 生態系
◇Efficiency 効率
◇Economic 経済的
の4つであり、資源を無駄遣いせず二酸化炭素の放出も抑えて地球に優しく、時間効率も良くてコストも引き下げられるということだ。
そして、もちろん、Antivirus、ウイルス感染対策にもなる。ウイルス感染対策はオマケみたいなものだ。新型コロナウイルスによるパンデミックが起こったことを契機に、コンタクトレス・アプローチに取り組むわけだが、感染予防はキッカケに過ぎない。いずれパンデミックが終息したとしても、4Eのメリットがあるのだからコンタクトレス・アプローチを増やして行きたいのだ。新型コロナの影響で、顧客が「会いたくない」「訪問しなくていい」と言ってくれることを逆手にとって、一気に営業改革を進めるのだ。
営業とは何か
ここで、そもそも営業とは何かという基本に立ち返ると、営業とは「自分の持っている価値を、相手に伝え、<お金をもらえる程のレベルで>その価値を認めてもらうこと」であると言える。それが営業だとすると、コンタクト(訪問して面談)するか、コンタクトレス(非接触・非訪問)かは、本質的な問題ではない。もし、それで営業部隊が必要なくなり通信販売で良いと考える企業があるなら、そうビジネスモデルを転換すべきである。しかし、多くの今現在営業マンを抱えている企業は、そうは言っても営業マンは必要だと考えるだろう。それなら営業マンはいても良いが、従来の訪問ベースのコンタクト(接触)営業ではなく、非接触のコンタクトレス・アプローチを取り入れたスタイルに転換するべきなのだ。
このコンタクトレス・アプローチは、ずっと社内にいることを前提としたインサイドセールスとは違う。イザと言う時、必要な時には客先にも行く。そうでなければ、「あぁ、あなたはコールセンターか何かの人なんだね」「TELアポ専門の人なんだね」と思われてしまって、商談が進めにくくなるからだ。だが、コンタクトレス・アプローチの方が4Eのメリットがあるから、安易には行かない。現場の営業マンは旧来のスタイルに戻る方が楽だから、つい行きたくなるだろう。行った方が話が早いと思うこともあるだろう。だが、ここはコロナウイルスのせいにして踏み止まる。コロナの脅威をプラスに活かすのだ。
話を営業とは何かという話に戻そう。通信販売でも良いはずなのに、営業マンが存在するのはなぜかを考えてみるべきである。顧客が何を買うかを決めていて、一番有利に(要するに安く)購入出来れば良いだけなら通販の方が安く出来る。それでも営業マンが存在するにはそれなりの理由がある。その理由とは営業マンの役割は何かということになるのだが、顧客を否定するか、顧客の考えを超越するのが、営業マンの仕事である。
多くの営業マンは顧客に合わせる、顧客のニーズに応える、顧客に好かれることが大事だと考えている。そんなことだから御用聞きしか出来ない。だが、新型コロナウイルスの感染リスクがあり、Amazonが何でも売るような時代には、御用聞き営業マンなど必要ないのだ。これからも必要とされる営業マンは、顧客の間違いを指摘し、より良い考えに導き、顧客が考えていなかったことを考えさせる。「お客様の仰せのままに」ではなく「いやいや、お客様、そういう考えは古いので、こちらの考えにすべきですよ」とサラッと否定して正しい方向にリード出来なければならない。
そのために、営業マンは顧客の顔色を伺う。表情の変化や間や微妙なニュアンスを読み取りながら上手に否定したいからだ。これが電話営業では出来なかったから対面営業が必要だった。しかし、顧客の顔色を伺うのを非接触で可能にしたのが、Web会議ツールである。ここが、コンタクトレス・アプローチの重要な点になる。従来からWeb会議、テレビ会議の仕組みはあったが、今ほど手軽ではなかった。画像も粗く音声も途切れたりして、顔色を伺うどころではなかった。だが今は、Zoomがあり、Teamsがあり、Meetがある。他にも色々あり、条件次第では無償で使えたりする。ほとんどのノートパソコン、すべてのタブレットとスマホには、カメラとマイクがついている。それでOK。準備完了。だから、コンタクトレス・アプローチを進めることが出来るのだ。すでに、Web商談をバンバン使っている企業も出て来た。緊急事態宣言でそうせざるを得なかった面もあるだろうが、もう世の中は非接触、コンタクトレスの時代に移っているのだ。是非、コンタクトレス・アプローチを試してみてもらいたい。
仮に、新型コロナウイルスのパンデミックがなかったとしても、人口減少による人手不足と顧客減少もあり、ICTの進化と普及、さらには「働き方改革」もあって、足で稼ぐ、人間関係で売る旧来の営業スタイルは通用しなくなり、コンタクトレス・アプローチ へのシフトは進んだだろう。そこにパンデミックがやって来て時計の針が一気に進んだ。
と思っていたら、すでに台風1号が発生し、梅雨が近づき、風水害の季節がやって来ている。毎年のように大きな被害が出ていることを思い出そう。ゲリラ豪雨や台風や線状降水帯によって電車が止まり、道路が通行止めになっても、コンタクトレス・アプローチなら営業活動を止めなくて済む。ウイルス対策だけでなく、事業継続のためにもコンタクトレス・アプローチが必要なのだ。
2020年5月
パンデミックをプラスに転じることができるか
新型コロナウイルスが、パンデミックとなり、経済効果も期待された東京オリンピックは延期となって、2020年は晴れ晴れしいオリンピックイヤーではなく、世界中を鬱屈させる暗い年になりそうだ。株価が下がろうとも、東京オリンピックが延期になろうとも、株も持っておらず、オリンピックのチケットも買えていなければ、直接的な被害はない。だが、外出を禁じられたりイベントを中止させられたりということになれば、全ての人に実害が出る。阪神淡路大震災の時の落ち込みも大きかったが、主に関西圏だけの問題だった。東日本大震災の時には、一時は全国的に自粛ムードが広がったが、ムードであってウイルスが広がったわけではなかったから、東北を中心とした被災地以外では回復も早かった。
日本が落ち込んでも世界経済が動いていれば外需に支えられる人も多かった。金融がパニックになっても一般の人の日常には大きな変化はなかった。そう考えると、今回の新型コロナウイルスの影響は、バブル崩壊よりも、リーマンショックよりも、3.11よりも、広くて深くていつまで続くか先が見えない。発症しても軽症の場合が多く、致死率も高くないのだから恐れ過ぎではないかとも思うが、その方が感染が広がりやすいと言う。パンデミックのメカニズムだそうだ。やっかいなものが現れたものだ。
問題はそこでどういう経営をするべきかである。自分一人のことだけを考えれば、すべての活動を自粛して引きこもっていれば良いが、ビジネスを継続し、収益を確保して、社員の雇用も守らなければならないとなれば、何でも自粛、何でも中止、というわけにはいかない。何とかして事業を継続させ、ビジネスを動かし、利益を確保しなければならない。
国が何とかしてくれるなどと思わない方がいいだろう。できるのは短期的な急場凌ぎくらいのもので、その財源はすべて、最後は自分達の懐を痛めるものだ。「国さん」とか「日本君」がいるわけではない。総理大臣や日銀総裁が払ってくれるわけでもない。無利子で貸してくれたとしてもいずれは返さなければならない。個人の月給にも満たないような一時金や商品券をもらっても大した足しにはならないし、借りた金を返済するには事業が継続していなければならない。
人の命が大切だというのは当然のことで、議論の余地もないが、肺炎でも人は死ぬが、経済でも人は死ぬ。年金をもらっている高齢者は、働かなくても一定の収入があるわけだし、肺炎の重症化リスクも高いわけだからウイルス感染を恐れるだろう。だが、現役世代は、個人事業や小規模事業者ほど働かなければ収入が途絶え、借金でもあれば悲嘆して命を絶つ人もいるかもしれないし、ウイルスには感染しても致死率は低いとなったら、肺炎よりも経済が怖いだろう。そう考えたかどうかは知らないが、某格闘技団体が、高齢者はあまり来ないであろうイベントを開催して批判を浴びた。キャンセルしても死ぬ、開催してクラスターが発生したとなったら社会的に死ぬ、どちらにしても死ぬ可能性があるとなったら、より生き抜く可能性を見出した、開催という意思決定を責められるだろうか・・・。どちらにしても命がけだ。
孫子の兵法には、『卒を視ること嬰児の如し。故に之と深谿にも赴く可し。卒を視ること愛子の如し。故に之と俱に死す可し。』という教えがある。部下である兵士を普段から赤ちゃんや我が子を見るように見守っていたら、決死の奮闘をしてくれるものだという教えだ。紀元前500年頃のことだから、兵士に人権はない。もし将軍が深い谷底への突撃を命じて、それに従わない兵士がいたら首を刎ねてしまっても誰も文句を言わない。だから死の恐怖によって兵士を動かすことが出来るわけだが、将軍の命令に従ったら死んでしまうという場面では、いっそ命令に背いて逃げてしまおうと考える兵士が出てくる。逃げて捕えられれば殺されるが、将軍が突撃するなら将軍自身が死ぬこともあるし、うまく逃げられる可能性もあるわけだから、命令に従って決死の突撃をするよりは生き延びる可能性がある。
要するに、死の恐怖によって人を動かそうとしても、その命令に従ったら死んでしまう確率が高いと思われてしまえば人は動かないということだ。新型コロナウイルスに感染したら死ぬかもしれないから外出せずに家にいろと言われても、その命令に従ったら収入が断たれて死んでしまうと思えば、命令に背く人が出てくる。
そこで問われるのが、リーダーシップであり、リーダーとフォロワーの信頼関係だ。このリーダーの示すビジョンに従った方が生きる可能性があると思わせるか、この人が言うなら、たとえ死んでも従おうと思えるかどうか。このコロナ危機に際して、首相や自治体の首長がこの人の言うことなら間違いないというリーダーシップを発揮できているかどうか・・・。政治の話は置いておいて、経営の道標としては、経営者がどういうリーダーシップを発揮するかを考えたい。
経営トップとして、このコロナ危機をどう乗り切るかというビジョンをまず社員に示すことが必要だ。普段からの信頼関係があった方がいいに決まっているが、今さら言っても間に合わない。この危機をどう捉え、どう判断し、どう対処するのか、指針を示し、企業としてどういう手を打つかを示して、社員を納得させなければならない。
そうなると、やはり必要となるのが、事業継続計画(BCP)だ。この経営の道標でも、地震や風水害が起こる度に、何度も必要性について述べて来た。大地震が来ても、津波が来ても、停電になっても、テロがあっても、戦争が起こっても、パンデミックが来ても事業を継続するにはどうすれば良いか、事前に備えてイザという時にも事業を止めないようにするべし、と。
だが、多くの企業で事業継続計画(BCP)が策定されていなかったり、策定していても、どこかのモデルを借りて来たようなありきたりのプランになっていたりするのではないか。今回の新型コロナウイルスに適切に対応し、事業を継続出来ているという企業は少ないように思う。
喫緊に必要なことは、会社に出社出来ない状態になっても、最低限の事業活動が継続できる体制を作ることだ。流行り言葉で言えばテレワークだが、自宅のパソコンを使ってWEB会議やチャットが出来ればいいみたいな話ではない。工場や店舗といった現場を持つ製造業や小売業、飲食業、サービス業においても、現場をクローズしても、最低限顧客や取引先に連絡したり、工場が止まっていても在宅で出来る設計、開発、デザイン、顧客折衝などは進めておくといった手を打って、事業の全面停止を避けなければならない。事業の一部でも動いているから、イザ復旧となった時のスピードも速くなる。
営業活動などは、動けるうちにWEBミーティングにシフトしておく。今なら「コロナもあるので」と言えば相手も納得してくれる。当然顧客情報の共有も必要となるし、見積書等の提示も出来る仕組みを用意したい。わざわざ紙に出力して上司に承認印をもらうなんてことは出来ないのだから。
事業が動けば経費もかかる。経費精算もテレワーク状態で可能にしなければならない。世の中はキャッシュレス時代なのだから、企業がやって出来ないわけがない。
お金が絡む話には、当然承認や牽制が必要になるから、ワークフローといった稟議決裁システムも必要になる。これらの仕組みや仕掛けは、NI Collabo 360やSales Force Assistantといったツールを使ってもらえば安価に構築出来るので、それが出来たら、就業規則の見直しもしておくように。自宅での就業における水道光熱費などの扱いを定めておく必要がある。長期的に在宅勤務をするようなら、PC等の業務環境を整えることも考えなければならない。
こうした体制を作った上で、事業をどう進めていくかというビジョンを示したい。店舗の在り方、工場の在り方、物流の在り方、営業の在り方なども見直し、新たなビジネスモデルへのチャレンジも必要だろう。毎年のように地震や風水害で事業継続が脅かされているのだから、コロナだけの問題ではなく、突発的な災害などにも強いビジネスを作っておきたい。
こうした道筋、ストーリーを社員に示そう。先が見えないのが一番困る。コロナ危機もいつまで続くのかが分からない不安が大きい。コロナ危機が続いても自社はこうしてこうなってこう生き残るというビジョンを示そう。
それが出来て、より強いビジネスモデルへの転換が出来れば、このパンデミックをプラスに転じることができたと言えるだろう。
2020年3月
2020年 庚子(かのえ ね)
これまでの努力が実を結び、新たな形が現れる年。東京オリンピックが実現し、オリンピック後の在り方が問われる年。令和時代の本格スタートとなる年。東京五輪の宴の後には、子供が少なく高齢者ばかりとなる日本のこれからの姿が浮き彫りになってくるだろう。繁栄とは何か、発展とは何か、幸福とは何か、新たな価値観が芽生え、過去の在り方を問い直す時代のスタートとなる年。
企業経営においては、人と企業、人と組織の在り方が変化し、「働き方改革」ではなく「雇用改革」をしなければならないだろう。知識労働が中心になると、人を金や時間でコントロール出来ない。給与を支払って一定時間拘束することに意味がなくなる。
「働き方改革」で残業を規制したり、同一労働同一賃金を強制し、定年年齢まで引き延ばそうとするなら、これまでのような雇用は出来ない。必要な時に必要な能力を持った人に必要なだけ仕事をしてもらうバッファを設けるしかなくなるだろう。そうなれば、今もてはやされているギグエコノミーは、働く側の好きな時に好きなだけ仕事をすればいいという自由よりも、求められる時に求められる人だけが求められるだけしか仕事をさせてもらえないという不自由をもたらす。
単純な作業で、反復するような仕事はAIやRPAやロボットに置き換えられて行くだろう。単純作業から解放されて創造的な仕事に専念できる人と単純作業の職を失ってヒューマンタッチを求められる職にシフトせざるを得ない人とに分かれて行く。そこでどういうビジネスモデルを描き、人と企業の関係をどうしていくかが、2020年代の大きな経営課題になるだろう。
雇用者と被雇用者、資本家と労働者、経営者と従業員という関係性から、個と個、人と人のつながりやパートナーシップ、協働、協調、共創による創発性が問われる関係になる。そもそも雇用もなければ定年もなく、解雇もない。個と個のパートナーシップなら、気に入らなければ離れれば良い。一緒に仕事をして心地良かったり新しいものを生み出す刺激がもらえるなら一緒に仕事をすれば良い。気に入らない人とイヤイヤ仕事をしていては創造的な仕事は出来ないから、相手もそれならロボットに置き換えたいと言い出すだろう。
企業は人と人とのネットワークになり、そのネットワーク全体が何らかのアイデンティティを持つ。それをCI(コーポレート・アイデンティティ)と呼ぶか、NI(ネットワーク・アイデンティティ)と呼ぶかは自由だが、企業という枠や箱(入れ物)が崩壊していくことは間違いないだろう。2020年はそういう時代の幕開けとなる年になるだろう。
2020年1月
経営の道標 年度別
経営の道標 2024年版
経営の道標 2023年版
経営の道標 2022年版
経営の道標 2021年版
経営の道標 2020年版
経営の道標 2019年版
経営の道標 2018年版
経営の道標 2017年版
経営の道標 2016年版
経営の道標 2015年版
経営の道標 2014年版
経営の道標 2013年版
経営の道標 2012年版
経営の道標 2011年版
経営の道標 2010年版
経営の道標 2009年版
経営の道標 2008年版
経営の道標 2007年版
経営の道標 2006年版
経営の道標 2005年版
経営の道標 2004年版
経営の道標 2003年版
経営の道標 2002年版
経営の道標 2001年版
経営の道標 2000年版
経営の道標 1999年版
経営の道標 1998年版
NIコンサルティングへの
お問い合わせ・資料請求