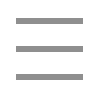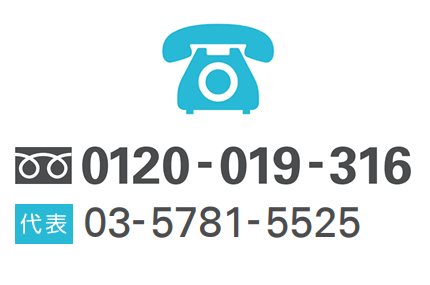代表長尾が語る経営の道標
2ヶ月に一度更新しています
2000年版 経営の道標
成果主義人事とプロセス評価
21世紀を目前に企業の人事制度見直しが増えてきた。このまま年功的な給与制度を継続していては21世紀に生き残ることはできないというわけだ。年功給を是正する職能資格給なるものが登場して久しいが、ほとんどの企業の実態は年功給に多少の色がつく程度のものであった。21世紀の日本は人口減少社会であり、無限の荒野は広がっていない。限定された市場で商売をしていく以上、毎年給与が増え賞与が増えるということにはなり得ない。したがって成果に応じた支払をするという成果主義の人事制度が必要だとなる。能力主義ではなく、成果主義だ。能力があるだけでは報酬が出せない。稼いでくれればそれに応じて報酬を出す。これは本来そうあるべきで、単に能力があってもビジネス上は意味をなさない。資格試験ならいざ知らず、能力があるかどうかで差をつけるのはそれこそ不公平だ。しかし結果や成果で差をつけるのであれば公平であり、誰しも納得せざるを得まい。
ただ、結果には運、不運がつきものであるという点で配慮が必要だ。成果主義人事への転換を図ろうという時には、必ずと言って良いほど、「営業部門など数字で結果が表される部門はいいが、総務などの業務は成果が測りにくい」という意見が出てくる。確かに結果を見るという点だけで言えば、その通りだ。しかし営業の成績は運、不運で左右される。逆に総務の仕事に運、不運はない。だから営業の仕事は結果だけでは測りにくく、総務などの仕事は結果で測りやすい。営業には「たまたま」ということがあるので、成果や結果だけでなくプロセスにも眼を向ける必要があるのだ。
成果主義人事というと結果だけを見れば良いのであって、プロセスを見る必要はないと考えるのが一般的だ。しかしそれは営業の実態を知らない人事屋の考えだ。特にこれからの営業活動は結果だけでなく顧客との間に共感、共鳴関係を築くプロセスが大切になる。ただ売れば良いのではないのだ。しかし売れなければ報酬は出せない。金銭的報酬は出せないけれども、プロセスについてはきっちりと評価してあげる必要がある。心的報酬を与える必要があるのだ。このことに多くの企業は気付いていない。それはSFA(営業支援システム)の導入をお手伝いしているからよく分かる。営業部門の改革を考え、IT化を進めている企業は、同時に営業部門の人事についても考えている。そしてのその全ての企業が成果主義人事を考えている。そしてプロセスは軽視しようとしているのだ。せっかくSFAを入れたのなら、それを使ってプロセスを見て評価する仕掛けを作ることだ。金銭的な報酬に結び付ける必要はないし、その余裕もないだろう。無い袖は振れないのだから。
営業活動に王道なし。正しいプロセス無くして正しい成果なし。ある時たまたま成果が出たとしてもそれは長続きするものではない。人事制度を成果主義にしたら売上が上がった、ということになったら非常に危ない。営業担当者が騙してでも売っている可能性がある。日々顧客の信用を落としている可能性がある。正しい営業改革、企業改革を21世紀に向けて行なっていただきたい。
2000年12月
不景気という言い訳を捨てよう
景気は回復軌道にあるとか、まだまだ実感がないとか、統計のマジックだとか、いろいろと景気談義があるが、そんな評論やデータの羅列に囚われることなく、経営者は今すぐ「好景気」を自覚すべきだ。少なくとも「不景気」ではないと考えねばならない。
冷静に日本の状態を見てみて欲しい。どこが不景気なのだろうか?自動車は新車ラッシュで伸びている。トヨタの最高級車セルシオが売れに売れている。それもグレードの高い型が売れていると言う。600万もするような車が納車待ちになる国が不景気なのか?海外旅行者は年々増えている。確かに格安航空券などを使う人も増えているだろう。行き先も近場になっているのかもしれない。しかしいくら格安の海外旅行とは言え、何十万かの出費はあるだろう。そのための時間も必要だ。時間も金もなければ海外旅行はできない。近場の温泉に一泊旅行するのとは訳が違う。その海外旅行が増えている。もちろんIT関連は絶好調だ。そのIT関連企業向けの工作機械などはバブル時期以上の活況とも言う。納期に間に合わず受注残が積み上がっている。ブランド物のブティックに行って見よう。どう見てもそんなに金を持っていそうに無い、若者のカップルが十万単位の買い物を嬉しそうにしている。どこで手にした金かは知らないが、確かに金を動かしている。就職難で大学生や高校生が就職できないと言うが、そんなに悲壮な顔をした学生に出会うことなどない。駄目ならアルバイトで食いつなぐか、留学するとか留年するとかまぁモラトリアムを楽しむという学生には出会うことがある。たくさんの学生がアルバイト市場に出てくるからアルバイトの時給が下がるかというと、首都圏では逆に上がっている。不景気で、職がないと騒いでいるのに時給が上がるのか?だからフリーターでも充分生活できる。そんな状況の中、政治家は愛人問題で揺れている。暢気なものだ。米が余っているから北朝鮮に援助すると言っている。それも外国産米ではなく国産米だ。その米を日本人はブランド米しか買わない。こしひかりとかあきたこまちでなければ買わない。ブレンド米は安くしても売れ行きが悪い。外国産米は店頭にも並ばない。こんな国のどこが不景気なのか。もし不景気だと考えているなら、自分の仕事の仕方が悪いか、自分の会社の経営が悪いだけだ。
今は物余りだ。日本は成熟経済になっている。そこそこの物、無くてはならない物はほとんど家に揃っている。だからそこそこの物をそこそこの売り方(値段)で売っていたのでは売れない。しかしユニクロは売れている。それは、そこそこの物が驚ろく安さで売っているからだ。100円ショップは大繁盛だ。これも同様、100円とは思えない物が買えるからだ。安いから売れているだけではない。良い物は高くても売れている。それがセルシオでありブランド品だ。良い物は高い方が売れていると言っても良いほどだ。
良い物は高くても売れる。そこそこの物でもびっくりするほど安ければ売れる。安かろう悪かろうが売れないのは当たり前だ。そして今、そこそこの物をそこそこで売る店や会社も売れなくなった。ただそれだけのことだ。決して不景気だからではない。景気の回復をただ待っていても、中途半端な商売をしていたのでは、いつまでたっても売れるようにはならない。景気の問題ではないから循環もしない。そのことに経営者は気付くべきである。
2000年11月
21世紀に向けて
21世紀まであと3ヶ月を切った。御社の21世紀戦略は構築済みだろうか。まだであるなら、今すぐ2003年乃至2005年までの中期経営計画を策定されることをお勧めする。21世紀に世の中がどうなるか、はっきりと予見できるわけではないが、既に明らかなこともたくさんある。2006年か2005年には日本の総人口が減少に転じる。これは間違いない。高齢化が進もうと少子化が進もうと口数自体が増えている間はまだ何とかなる。しかし総人口が減るということは明らかに総需要を押し下げる。三度三度の食事も減る。住宅も減る。着る服も減る。備えているだろうか。
2001年には新規格の携帯電話が登場する。伝送スピードが大幅に向上し、動画も送れるようになるという。コミュニケーションのあり方が変わるだろう。そしてビジネスのあり方も変わるだろう。備えているだろうか。
2003年にはネット上で税務申告ができるようになる。ネット上での行政サービスがスタートする。いわゆる電子政府だ。大きな変化が起こりはしないか。IT、ITと騒ぐ時代ではなく、当たり前のものになっていくだろう。備えているだろうか。
これからの企業経営は一段上のレベルを目指す必要がある。これまでの延長線上で経営を見てはならない。その基本は自社のコア・コンピタンスである。自社ならではの価値をいかに作り、高めていくか、という課題に取り組むべきである。あなたの会社に「自社にしかできない固有の技術やサービスや製品」があるだろうか?あれば、それを高め、広め、収益に結び付ける方法を考えよう。もしなければ、深刻な危機感をもってコア・コンピタンス構築に取り組まなければならない。既存の事業が収益を上げている間に急いで準備しなければならない。21世紀になる前に「これで行こう」という方向性だけは明確にしなければならない。
そうでなければ、2002年の新卒採用ができない。今や採用はインターネットで行なわれる。10月には2002年度新卒の就職情報サイトが立ち上がりサービスを開始する。2001年が明ければ就職活動は本格化する。その時、学生達に21世紀のビジョンを語れるだろうか?2002年、2003年の自社の姿がある程度明確になっていなければ、優秀な人材など採れはしない。
今は就職氷河期などと言っているが、学生数自体も減っていることを忘れてはならない。IT企業はIT学生を大量採用しようとしている。IT時代にITが分かる人材が欲しいのはどこの企業も同じ事だろう。備えているだろうか。
21世紀に向け、経営者には戦略思考が求められる。3ヶ月間智恵を絞ってみたい。
2000年10月
社員一人ひとりの自立
乳業メーカーY社の食中毒を発端に多くの大手企業で異物混入やクレーム隠しが明らかになっている。錚々たる企業であり、「あの会社までもが」と感じることも多い。消費者は企業への信頼感を損ないながらも、仕方なく購入を続けている。「他にないから仕方なく」買っている状態は企業にとってもっとも危険な状態だ。数字は大して落ちていない。しかし顧客の支持は確実に失っている。そのことに経営トップは全く気付いていない。現場の声を聞き、顧客の「声なき声」を聞かねばならない。
一連の事件、事故を通じて考えなければならないのは、現場の声を吸い上げ、情報共有することとともに、現場の一人ひとりの社員が一企業人として自立し、経営感覚をもつことである。数ある工場の中の、多くのラインの中に汚れたバルブがあるかどうかまで、経営トップが知ることはないだろう。それはどんなにIT化が進み、情報共有されたとしても、そこまで知っておくことは不可能だ。しかしいったん事故がおきれば「知らなかった」では済まされない。現場の作業員が当たり前に、決められた通りに作業をしていてくれれば、汚れていなかったのだ。恐らく現場では、「これくらい大丈夫だろう」「俺一人くらいどうってことないだろう」と考えていたに違いない。この現場の判断に企業が存続の危機に立たされる。現場の一担当者の判断が企業を左右するのだ。すなわち経営トップの判断と同等の重みを持つことがある、ということである。
一般の社員が「自分の判断が企業を揺るがすものになる」と考え行動しているだろうか。一般の社員どころか管理職までもが同様ではないか。現にY社の場合には工場長までが同じような判断をしていた。それを最後まで社長に報告もせず、記者会見で吐露するという失態を演じている。多くの社員が「作業員」となり言われたことを言われた通りにもしないのでは、事故や事件が起きて当然だ。今こそ各企業の現場の一人ひとりに自覚が求められる。一社員、一担当者であっても自分の意思決定によって企業全体が動くという事実を認識する必要がある。社員個人が企業であり、企業は個人なのだ。部分と全体は一体不離の関係にある。
個々の社員が自らの価値と役割を自覚し、その個々の価値を認め権限を委譲する経営が望まれる。どんなに経営者が立派であっても現場のバルブの汚れまでチェックすることはできないのだから。
2000年8月
SFAさえあれば良いか
SFA導入コンサルティングをしていて感じることがある。それは「SFAを入れればそれで売上があがる」と簡単に考えている人や企業が多いということだ。もちろん、それは間違いだ。SFAを導入しても誰も日報入力しなければ意味はないし、入力しても読まなければ無駄である。そして最も多いのが、読んで終わり、という企業だ。これもまた意味がない。SFAというのは単純に言えば、営業現場の声、すなわちお客様の生の声を収集してくるシステムだ。今まで営業担当者の属人的な情報として勝手に処理されていたクレームや成功事例が中間管理職のバイアスをかけることなく、全社的に収集整理される。しかしそれを生かすも殺すもそれを読む人次第。これはシステムの限界を超えている。顧客の生の声を経営に活かそうという気がある企業ではSFAは大きな威力を発揮する。しかし顧客志向とかお客様第一主義というのは自分たちの業績を上げるためのご都合主義で唱えているに過ぎない企業では、いくら顧客の情報が収集されても何も生かされない。何をするかというと営業担当者の行動管理だ。営業担当者の行動と顧客の声は表裏一体だから、どちらに重点をおくかで同じ情報(日報に書かれた同じ言葉)でも、受け取る意味が違ってくる。
営業現場ではないが、今大きな問題になっている雪印の牛乳も同じことが言える。階層毎に言うことが違う。同じ事を言っても解釈が違う。伝わっているようで、事の重大さが伝わっていない。分かっているつもりだけど分かっていない。この分かっているつもりが問題だ。初めから分かっていないと思えば記者会見で右往左往するようなことはないのだ。分かっているつもりでいたことが事実とは違うことに会見の席上で気付くとは情けない限りである。
SFAは営業担当者が存在する企業において、絶対不可欠のツールである。これなくして顧客の声を吸い上げることもできないし、何より全社的に活用していくことができない。今時、紙の日報を書いたり、口頭で直属の上司にだけ報告していたのでは通用しないのだ。当該部署だけで解決できる問題などそう多くはないし、解決できたとしてもたかが知れている。そういう意味で、「SFAを入れれば売上があがる」という表現は正しい。但し、ただ導入しただけでは売上は上がらない。SFAの意義と位置付けをしっかり理解し、各人が本当に顧客の声を尊重する意識をもった時に業績向上のツールとなるのだ。
SFAを導入したものの、うまく運用できていない、うまく活用できていないという企業は少なくないはずだ。今一度、自社の取組み姿勢を見直してみていただきたい。
2000年7月
経営のあるべき姿
あるクライアント企業の将来ビジョンを作成していて、改めてITの必要性を実感した。今後の環境変化を考えながら、市場の推移を予測し、打つべき手を挙げて行くと、ほとんどがITがらみだ。何かしようと思うと、どうしてもコンピュータに関することになってしまう。「これからの経営はコンピュータなしでは考えられない」とは良く聞く言葉でもあり、私自身も良く使う言葉ではあるが、全部門に渡ってIT施策が必要になってしまうというのも、これからの経営のあるべき姿を考える上で、考えさせられることだった。
これまでの将来ビジョンと言えば、まぁもっともらしい理屈はつけるものの、業界のトップ企業に近づけようとか、どこかの経営指標を持ってきて平均値まで改善して行こうとか、とにかく手本というか目安があって、その中で取捨選択していくことで形になったものだ。中小企業診断士の診断などはまさにそういうもので、現状を分析するというのも平均値の指標との誤差を明らかにすることであり、それから逸脱したら問題点として指摘する。そしてどうするべきかというとまた平均値の指標があって、それに近づけていくことが課題となる。それでは一生、競合他社を出し抜いて、業界トップになどなれないのだが、永遠の弱者である中小企業が相手なのだからそれで良しとされてきたわけだ。しかしその診断士制度を支える中小企業基本法が改正になり、中小企業を弱者と決めつけず、強くこれから伸びて行く企業もあれば、そうではない企業もある、という前提の下に伸びようとする企業を支援するということになった。弱肉強食を後追いではあるが国も認めた格好だ。
あるべき姿のないビジョン作りはオリジナリティが必要なだけに難しい。特にネットを使ったことを考えれば、他ではやっていないことをやらざるを得ないことになり、これまでのやり方では通用しない。そして何より難しいのは、当事者である社員が考えられないということだ。インターネットを使ったことのない社員を集めて、「さぁこれからネットの時代ですよ」と言ったところで、どうするべきかなど考えられない。じゃあIT技術を使ってこういう仕組みを作りましょうということになっても、実際にパソコンは配備されておらず、あっても使えず、というのでは話しにならない。せっかく作ったあるべき姿もそれを実行して行くためには予想以上の時間がかかる。ここが既存企業の弱みだろう。既存企業には既存事業という強みがあるが、人がいるだけに変化のスピードが遅い。逆に若いベンチャー企業は安定した収益基盤はないが、ITを使うことなど当たり前のことだ。新しい人ばかりだから、どんどん新しいことにチャレンジしていける。
企業経営者には、改めて将来ビジョンの構築が求められると同時に、一日でも速いIT化への取り組みが求められる。コンピュータは買えばすぐに動くものではないのだ。ネットは頭でいくら考えても活用できるものではないのだ。
2000年6月
終身雇用
新卒採用が佳境に入ってきた。未だに新卒の定期採用か、とも思うが、日本における人材確保において、新卒採用はまだ欠かせないものだろう。優秀な人材をより低いコストで確保する非常に有効な方法である。短期集中で一年先の採用を決めるのは大変な労力とリスクがあるが、逆に言えば、短期集中で業務を処理することができるとも言える。就職情報誌やDMからインターネットへと採用方法は完全にシフトし、採用業務の効率化も図られるようになった。学生の意識も大企業一辺倒からベンチャーや中小へ向きつつあり、少子社会に向けて今のうちに採用体制を整備することも必要だろう。
そうした採用活動の中で、どうしても考えておかなければならないのが、終身雇用の終焉ということだ。新卒の社員だからといって、定年まで勤めてくれるとは限らないし、企業側もその保証はできない。ということは、これまで「素材を買う」という意味合いの強かった新卒採用においても「短期促成栽培」可能な、即戦力とまではいかないまでも、短期的に力を発揮しれくれそうな人材に絞って採用しなければならない。「使えるかどうか分からないが、とりあえず採用しておこう」というような余裕はないし、そもそも学生にとっても不幸なことだ。当分冷や飯を食わされるかもしれないところに採用されたからと言って喜んではいられない。それが仮に有名企業であってもだ。終身雇用を前提としない以上、雇われる側にとっても短期的に成果を挙げられる企業に入るべきである。そうしなければ成果主義の人事の下で処遇を上げていくこともできない。
新卒だからといって甘やかせるようなことはせず、すぐに成果を求めることは新入社員のためである。そのことを採用活動の中で明確に宣言しておくことをお勧めする。当社は終身雇用ではなく、年功序列でもなく、新卒だからといって何年も研修期間があるわけでもない。完全に実力によって処遇は決まるのであり、それについて来れない人には去ってもらうこともあるだろう。こういう説明は何度もした方が良い。雇用や処遇などは企業が保証できるものではないのだ。顧客が決めることなのだ。顧客が満足しそれに対する対価を払ってくれない限り、雇用することも昇給することもできない。
既存の社員に対する意識改革も必要だが、これは過去の積み重ねがあるから大変だ。しかし新卒はゼロからのスタートだから、そういうものか、で納得してくれる。かえってその方が優秀な学生にとっては魅力がある。新卒だから時間がかかる、と考えず、新卒だから実力主義、成果主義でやっていける、と考えてみよう。
企業セミナーで、面接で、終身雇用の終焉を高らかに宣言して欲しい。
2000年5月
新入社員を組織活性化に結び付けよ
春らしくなり新入社員の季節となった。通年採用や中途採用へのシフトがあって、4月に新入社員という固定的な考えも見直されつつあるだろうし、新規の採用を手控えている企業も多いかもしれないが、やはり春は新入社員のシーズンであり、大半の企業にはフレッシュな新人が入ることだろう。
すぐには役に立たない、社会人としてのマナーも知らない新卒を採用することは、確かに米国流、グローバルスタンダードに照らすと、あまり誉められたものではないかもしれないが、現状の日本企業には仕方のないことでもあると言える。反面それが新卒採用の良い面でもあるわけで、要は新卒採用を活かすか殺すかという問題だろう。
特に中小企業やベンチャー企業においては、最も安く、より優秀な素質を採用する方法が新卒採用であると思う。中途の経験者をヘッドハンティングできるほど余裕があったり、上昇気流に乗っていれば問題ないだろうが、多くの企業にはちょっと高価過ぎる。一念発起して採用しても中小企業でその能力を十分に発揮しきれないという事例も数多く見てきた。中途採用も必要であり、もちろん即戦力になるのは中途採用だ。だからと言って新卒を採用しないというのは間違いだと思う。バランスが重要なのだ。
その新入社員を既存の組織に投げ入れることで、新しい風を作っていくことが求められる。新卒はビジネスのことが分かっていない。だから素人にも分かりやすい様に説明したり資料を作らなければならない。この時、お客様は素人であることを思い出そう。
新卒にはマナーを教える。二年目の社員にマナー教育をさせてみよう。成長を実感するかもしれないし、過ぎた一年を反省するかもしれない。新卒は素直で前向きだ。自分にもそうした時期があったことを思い出そう。そんな新卒も2ヶ月、3ヶ月と経つ内に後向きな不平不満を口にしてせっかく覚えたマナーも崩れてくる。そうさせているのは周囲にいる先輩社員だ。新入社員にとって一生に一度の社会人としてのスタートを踏みにじる企業があることは非常に残念なことだ。
私は毎年3月、4月と様々な企業の新入社員研修で忙しいが、不思議にその間は元気である。今もどんな新入社員達と会えるか楽しみだ。素直で前向きで、仕事に対して不安と自信を持っている新入社員にいろいろなことを教えてあげたいと思う。
皆さんの会社にはどんな新入社員が入って来るだろうか。またその受け入れをどのように行なうのだろうか。
2000年3月
情報発信力
iモード携帯へ日替わりメッセージが配信されるメールマガジンに登録した。最近では手放すことのできなくなった携帯電話に毎日日替わりで情報が届けられる。私は毎日、経営の格言が送られるというメールマガジンに登録したのだが、他にも多岐に渡るメールマガジンがある。通常のメールではなく、携帯に届くというのが良い。それも携帯用だからメッセージが簡潔だ。一般のメールマガジンも読んでみたことがあるが、量が多くて読むのが大変だ。ちょっと溜めてしまうとそれこそ読めなくなってしまう。その点、携帯電話であれば常に持っており、ちょっとしたスキマ時間に読むことができる。
メールマガジンは一般にWEBサイトへのマーケティングで行われるが、まさにこれからはコンテンツ、情報提供の中身で企業間の勝負が決まるようになるだろう。如何に自社の持つ価値を見込み客、ターゲット層に伝えるか、そしてそれを継続していけるかがポイントとなる。ホームページを作ることは簡単で、ちょっと本でも読めばすぐにできるようになるが、その中身がどうかと言われると難しい問題だ。特にインターネットの世界は情報の鮮度が問われる。日替わりとまではいかないまでも、週単位、月単位で更新し続けなければならないし、メールでもくれば返答もしなければならない。その中で価値があると認めてもらえた企業だけに見込み客が顧客情報を教えてくれる。
と、書いているこのサイトも、ご覧になっている皆さんに評価されているだろう。価値があると思えば、他のページも読んでもらえるだろうし、資料の請求でもしてみようという気になるかもしれない。しかし、パッと見て、二度とこのサイトに来てくれない人もいる。企業の情報発信力を高める取り組みが今すぐにでも求められている。
IT投資はハードの投資だけでなく、人への投資も欠かすことができない。そしてその闘いはすでに始まっている。
2000年2月
庚辰(かのえたつ)
2000年は、庚辰(かのえたつ)。剛健にして陽、奮迅隆(龍)起する年となる。変化が激しく、波風も高いだろうが、前方、上方への揺れであることを信じたい。
今年、どうしても取り組まなければならないこととして、インターネットを挙げたい。昨年1999年は日本のインターネット通販元年と言われたが、現実には今年2000年が本格スタートの年になるだろう。インターネットの世界は先手必勝である。マーケットが大きくなり、確実に成果が出始めてからでは遅すぎる。今すぐ、自社の既存事業とインターネットの融合を検討し始めなければならないだろう。
インターネットとは縁も所縁もないような、我々のクライアント企業でも、具体的な取り組みを始めており、今年はそれを本格化させる予定である。どんな企業でも、業種業態を問わず、ネット化の余地はある。新しいビジネスモデルを構築するチャンスがあるのだ。特にここで重要なことは、世界を狙わないことだ。インターネットというとどうしても世界を相手にしたくなるものだが、未だにインターネットビジネスに乗り出していないような企業が、世界で闘うのはなかなか難しい。それよりも地域に根差した、本業との相乗効果のあるインターネット活用を行うことを最優先で考えることが必要だ。
インターネットビジネスのポイントは、顧客との双方向コミュニケーションとそれによる顧客理解である。顧客を知り、その顧客(個客)に対して個別・特別の対応を実現することが、インターネットビジネスの基本だ。それは既存の商売、接客においても同様であるが、面と向かって話をしないだけに、より以上の顧客理解が求められることになる。
そしてこのインターネットビジネスは自分一人、自社だけでやろうとしてはいけないということも重要なポイントである。一社だけでは絶対に成り立たない。ホームページの制作に始まって、回線の問題、電子決済の問題、セキュリティーの問題、物流の問題等々、到底一社だけでは解決できない課題を乗り越えなければならない。だからといって諦めるのではなく、アウトソーシングを活用するべきだ。実際にリンクソーシングにおいても、e-ビジネスアウトソーシングを行なっているが、昨年末から引き合いが続いている。そこでも我々だけでは無理だから、様々な企業との連携を図って実現しているのだ。
2000年はIT投資がキーになろう。その中でも特に重要なものがインターネットである。広告、広報レベルの活用ではなく、実際のビジネスをインターネットにつなげる時が来たのだ。
2000年1月
経営の道標 年度別
経営の道標 2024年版
経営の道標 2023年版
経営の道標 2022年版
経営の道標 2021年版
経営の道標 2020年版
経営の道標 2019年版
経営の道標 2018年版
経営の道標 2017年版
経営の道標 2016年版
経営の道標 2015年版
経営の道標 2014年版
経営の道標 2013年版
経営の道標 2012年版
経営の道標 2011年版
経営の道標 2010年版
経営の道標 2009年版
経営の道標 2008年版
経営の道標 2007年版
経営の道標 2006年版
経営の道標 2005年版
経営の道標 2004年版
経営の道標 2003年版
経営の道標 2002年版
経営の道標 2001年版
経営の道標 2000年版
経営の道標 1999年版
経営の道標 1998年版
NIコンサルティングへの
お問い合わせ・資料請求