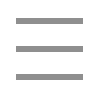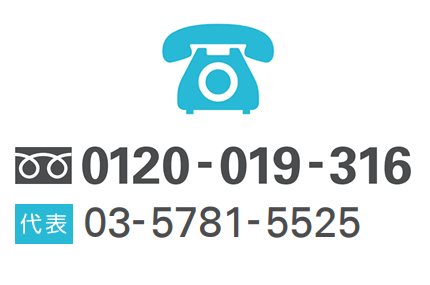代表長尾が語る経営の道標
2ヶ月に一度更新しています
1999年版 経営の道標
コア人材の見極め
アウトソーシングの仕事の中で、社員個人の専門性やキャリア形成についてカウンセリングすることがある。そこでは転籍を促すこともあるし、退職を勧めることもある。「今のままではあなたの専門性が活かされませんね」とか「ここでのキャリアがあなたのプラスになりますか」などと話していくわけだが、そこでその本人の会社に対する考え方、仕事に対する考え方が明らかになる。
アウトソーシングが浸透してくると、本人の持つ能力よりもその会社との一体感をどれだけ持っているかが社員としては求められる。能力は簡単に金で買えるようになるからだ。単に会社や上司に盲従するような忠誠心は意味がないが、会社を良くしよう、組織全体の価値を高めようという姿勢があるか、ないかはコア人材かどうかを見極める上で非常に重要である。
今はあまりにも自分中心、自分のことだけを考えている人が多すぎる。自分さえ良くなればそれで良いと考える人はそういうことが許される会社に移るべきであって、会社をだまし、上司をだまし、最後には自分の心もだましてしまうような働き方はお互いのためにならない。企業には必ず間接部門が存在する。間接部門はその企業の主流にはなり得ない。そこでどんなに専門性を磨こうとも、その専門性だけではなかなか存在価値を高めていけない。そういう人はアウトソーサーへの転籍なども積極的に考えてみると良い。企業の側、経営者の側もそういう人を企業の都合だけで飼い殺してはならない。
そうした取り組みの中で、「この会社が好きだから」「社長と一緒に仕事をしたいから」といった言葉を発する人材はその企業にとって金では買えない存在である。どんなに本人にとって都合の良い話を聞かされても、やっぱり組織のこと、会社のことが気になってしまう。そういう人材をもっと活かすべきである。去るのも良し、残るのも良し。一度コア人材の見極めをしてみられることをお勧めする。
1999年10月
甘えは許されない
興銀、富士銀、第一勧銀がひとつになって6000人を削減すると言う。まさに金融ビックバンが本格化してきた証拠だろう。東京電力とソフトバンクとマイクロソフトが公衆電話回線に依存しないインターネット接続会社を作ると言う。面子やこだわりを捨て、21世紀にどう生きるかを超大企業であっても真剣に考え始めた証拠だろう。
その一方で、万年赤字に甘んじている中小企業が無数にある。業績の悪化にも関わらず、何ら抜本的な手を打つでもなく、ただ昨日と同じことを今日も繰り返す。故意に赤字の決算にしている企業を除いて、そうした企業の経営者はとても経営者とは言えない存在である。どんなに複雑な経営手法が出てこようとも、企業の損益計算は足し算と引き算だ。入ってくる収入よりも出て行く費用が多ければ赤字となる。入ってくる収入が減れば、出て行く費用を少なくすれば良い。業績が悪化したらすぐにリストラで経費削減だと考えるのもレベルが低いが、業績低迷が続いているにも関わらず、経費削減にも取り組まないというのは論外である。
頑張っているけど利益が出ない。というのは働き方が悪いのだ。儲け方が悪いのだ。自分本位に頑張っているだけなのだ。業績数字は大人の通信簿である。通信簿に文句をつけても仕方がない。どんなに頑張っても赤点が返ってくるなら、頑張り方を変えるしか手はないのだ。
特に問題となるのは人件費だ。人件費が過多で利益が出ないということは、従業員の働きが悪いのだ。どんなに頑張っているように見えてもそれはお客様に受け入れられない頑張りであり、実際に万年赤字の企業の従業員がお客様のために誠心誠意、骨身を削って頑張っているようなことはない。本当にそれほど頑張れば赤字が続くはずがないのだ。
お客様に喜んでいただけるような仕事ができない人間には辞めてもらわなければならない。少なくとも自分の付加価値に見合うだけの給与まで引き下げる必要がある。ローンもあるだろう。家族もいるだろう。生活もあるだろう。しかし彼らはそれに見合う価値を世の中に対して創出していないのだ。
すべての社員を平等に扱うというのは結構なことではあるが、それは、それができる業績の良い中小オーナー企業の経営者がやることである。普通の経営者は社員を公平に扱う。価値を生む人にはそれに見合うだけの報酬を与え、価値を生まない人にはそれなりの報酬しか出してはならない。某大手宅配業者では一定の時間を過ぎて仕事をしていると給料が減額されるそうだ。普通の会社であれば残業手当をつける仕事に対してである。
遅くまで仕事をする人の給料を減らすことまでするかどうかは別にして、経営者はもっと冷徹に現実を見つめる必要があるだろう。価値を生まない人間まで何とかしようとしている間に、頑張って価値を生んでいる人に負担をかけることになる。最悪の場合、全員を倒産という憂き目に合わせることになってしまう。
金融機関も今までのように優しくはない。自分たちがどうなるか分からないのだ。特別保証も結局は単なる延命策でしかない。赤字企業は世の中に価値を生み出していないという現実を直視し、経営者は断を下すべきである。ベンチャー育成のために、倒産しても再チャレンジできるセーフティネットを作るというような、分かったような分からないような話もあるが、倒産という事実は消せないし、社員や取引先に迷惑をかけるということは間違いない。甘えは許されない。
1999年9月
ナレッジ・コラボレーション
ナレッジマネジメントに関する解説書もかなり出版され、ようやく市民権を得つつあるようだ。ナレッジなる日本人に理解しづらい言葉を、小難しい論理で説明されると勘弁してくれと言いたくなるが、かなり簡潔に説明した書籍も出てきた。このナレッジマネジメントは、日本企業の雇用形態の多様化ともあいまって、今後必須の経営課題となっていくだろう。
長引く景気低迷、経済のグローバル化、経営のスピードアップ、キャッシュフロー経営、産業構造転換のための雇用流動化など、枚挙に暇がないほど、企業のスリム化を推し進める環境変化が起こっている。そのため、単純なリストラ(人員削減)は今や当たり前となり、社員数が減った後は、雇用形態の多様化が必然となりつつある。
人材派遣は既に当たり前のものになったが、アウトソーシング、契約社員、パート・アルバイト、SOHO、短時間勤務なども少子高齢化の進行とともに比重を増している。人材派遣はこれまで26職種に限定されていたが、来年からはネガティブリストによる原則自由化が行われ、アウトソーシングサービスを提供するアウトソーサーはもの凄い勢いで増加している。企業のコア部分を担当する正社員は当然必要だろうが、その周りをサポートする人間は非正社員となり、別会社の人間となる日も近いだろう。
そういう時代になれば、これまで長期安定雇用を前提に正社員を確保し、彼らの個人的経験やノウハウに頼って業務を進めていた企業は困ったことになる。個人の頭や手帳に隠されている智恵やノウハウを形式化(文字や図形に表す)し、それを活用する仕組みを作らなければならない。正社員でも非正社員でも自由に活用できる智恵のデータベースを作ることで、企業の知的資産の蓄積と運用を行うべきだろう。
そういう背景があって、ナレッジマネジメントという概念が注目を浴びているわけだが、これがなかなか難しい。知識はともかく智恵というのは簡単に文字や図形で表すことができないからだ。そこでナレッジマネジメントでは、形式知と暗黙知という言葉が出てくる。形式化された形式知はコンピュータにも載り易いし活用もしやすいから良いのだが、形式化できない暗黙知がやっかいだ。ちょっとしたコツやニュアンスというのは伝え難いものである。しかしそこにこそ価値があるものでもあり、何とかしてこの暗黙知を共有し活用する仕組みを作りたいものだ。
そこで提案したいのが、ナレッジ・コラボレーション。簡単に言うと数人が集まって、ワイワイガヤガヤやりながら智恵を出し合い、その過程で智恵を共有し、新しい智恵を生み出そうというものだ。ホンダのワイガヤ経営と同じ事か、ということになるのだが、これをコンピュータ上で行う。コンピュータ上でコラボレーションするということだ。その過程はすべてデジタルデータで保存され、後から活用することも簡単だ。何気ない会話の中や失敗談の中に暗黙知が潜んでおり、それを共有する環境を作ることで、言葉で表現できない智恵を伝えることができるようになるのだ。すなわち行間を伝えるということである。そのベースには共通体験、信頼感、共通の目標がなければならないが、こうしたコラボレーションの場と道具を提供し、コーディネートしていくことがナレッジマネジメントの具体的手法であるとご理解いただきたい。コンピュータのシステムだけでは実現できないことをどれだけの情報担当者が理解してくれるかが心配なところではあるが、知識と智恵の違いについて考えれば必然でもある。ナレッジ(知識・智恵)のマネジメントと考えずに、場のマネジメントであると考えた方が近道かもしれない。
1999年7月
営業プロセス改革に着手せよ
SFA導入に関する御相談が増えてきた。私もますます「SFAの導入は必然である」という確信を深めている。人間の頭や紙では処理しきれない情報をSFAは整理し、飛躍的な営業革新を実現してくれるからだ。
しかし未だ、SFAを営業マンの行動管理、効率管理に使おうと考えている企業が少なくない。訪問軒数や電話本数、商談時間、移動時間を管理するだけでは成果は上がらないといくら説明しても、過去の「足で稼いだ」成功体験から抜けられず、せっかくのコンピューターを事後管理に使ってしまう。これでは営業マンはたまったものではない。そして情けないことに、訪問軒数が増えたり、電話本数が増えたことを「営業の生産性が上がった」と誤解しているから滑稽だ。
生産性とはインプット(投入量)に対してどれだけのアウトプット(産出量)があったかを示す指標である。したがって生産性を上げるには、インプットを減らしてアウトプットを増やすことが必要だ。であるならば、営業の生産性は訪問軒数や電話本数というインプットに対して売上・受注というアウトプットがいくらあがったかを示すものであり、訪問軒数や電話本数を増やすことはインプットを増やすことだから生産性が落ちることになる。
かつてはマーケットに無限の荒野が広がっており、営業活動のインプット(訪問軒数や電話本数)を増やせば、それなりにアウトプットがあがった時期もあった。しかし今や、どんなに頑張っても、頑張るだけでは売上があがらない成熟経済に突入しているのだ。
訪問軒数や電話本数を増やす、すなわち営業マンの活動量を増やすということは、営業の生産性を上げるものではなく、営業マンの回転効率を上げることに他ならない。営業マンの人件費をインプットとし、それに対するアウトプットを活動量であると考えれば、確かに生産性の尺度として読めないわけではない。しかし我々は活動ではなくその成果を求めている。やはり成果に対する生産性を論じるべきであり、手段の生産性をいくら上げたところで、最終の目的を果たさなければ意味をなさないのだ。
このことを考えると、営業の改革にプロセス改革が求められることが分かる。プロセスを組み替え、訪問軒数や電話本数などのインプットを減らして、アウトプットを増やす仕組みを作らなければならないのだ。
その最大のポイントは、見込客の見極め(案件化)を顧客訪問後から訪問前に持ってくることだ。すなわち「行って→売る」から「売れる→行く」へのパラダイムシフトが必要だということだ。見込みのないところにとにかく行って、無理をして売るという営業スタイルから、売れるところ、売れる見込みがきちんとあるところだから、きちんと準備をして売りに行くという営業スタイルに変えるのだ。
このプロセス改革で営業の生産性は劇的に向上する。SFAを営業マンの行動管理に使い、生産性を落しながら無駄なコストをかけるようなことをせず、営業プロセス改革に活用しなければならない。
SFAは行動管理ツールではなく、営業革新ツールなのだ。
1999年6月
売り手と買い手の一体化
CRM(カスタマーリレーションシップマネジメント)やSCM(サプライチェーンマネジメント)、SFA(セールスフォースオートメーション)、CTI(コンピューターテレフォニーインテグレーション)など最近話題の情報化キーワードを見ていると、そこには売り手と買い手の一体化という本質的な営業・販売構造の変化が読み取れる。表層にある最新技術やコンセプトに着目してしまうと、未だ時期尚早であるとか、自社には関係ないという感じで受け止めてしまいがちだが、それが自社もしくは自分にとって時期尚早か直接関係あるか否かに関わらず、この変化の潮流を見極めておくことが重要である。
従来、売り手と買い手、営業マンと顧客、販売員とお客様の関係は対立関係として捉えられていた。敵対関係とまでは言わないまでも利害の反する存在であり、互いに腹を探り合い、駆け引きをしながら取引を成立させていく関係であった。CSや顧客第一主義を浸透させようとして営業マン研修や販売員教育に乗り込むと、参加者からは「そんな奇麗事を言っていては利益が取れない」とか「すべてが良いお客様ばかりではない」といった否定的な意見が返ってきたものだ。確かにお互いの利害が反する面があることは否めず、CSや顧客第一主義が掛け声だけで終わってしまったことにはそれなりの理由があると言わざるを得ない。
しかしここに来て再度、CS経営、顧客第一主義が求められている。マーケットの縮小と成熟化、そして情報通信技術の進歩によるものだ。マーケットが拡大している時には、新規開拓でどんどん業績を作っていくことができる。しかしマーケットが縮小していれば、新規開拓の余地はすぐになくなり、既存客を掘り起こし、新たな需要を創出していくことができなければ、業績向上を実現できない。そのためには、顧客をもっと知らなければならない。顧客を知り、顧客が何を求め、何に対して価値を感じてくれるのかを知ることが必要となる。そこで出てきたキーワードがCRMであり、企業版CRMがSCMである。そしてそれらを実現するツールとしてSFAやCTI、CALSなどが取り上げられている。これらは10年前にはSIS(ストラテジックインフォメーションシステム)として一括りになっていたが、当時はまだ情報通信技術やインフラが十分ではなかったため、単なるコンセプトで終わってしまった。これが現実に実現可能になるにしたがって新しいキーワードで化粧直しをして登場してきていると考えても良いだろう。
そうした経緯はともかく、重要なことは、この動きが売り手と買い手の一体化を進めていくものであるということだ。売り手が買い手について知る為には、買い手が売り手を信用して自分の情報を提供しなければならない。買い手と売り手が交渉し駆け引きをする際に使ったカード、すなわち、購入時期、予算、意思決定権者、競合状況、仕入価格、製造原価、物流コストなどの情報を相手に対してオープンにし、相互に信頼し合える関係を築かなければならない。これは単にコンピュータを活用すればできるというものではない。パラダイムの転換が求められるのだ。
新しいビジネス形態、新しい取引関係、新しい販売概念が求められる今、企業にはより本質的な議論と改革が必要だろう。
1999年4月
キャッシュフロー経営
2000年の3月期から、上場企業にキャッシュフロー計算書の提出が求められることを受けて、キャッシュフロー経営なるものが関心を集めている。書店にはキャッシュフローコーナーができ、新聞、雑誌でも特集が組まれたり、関連記事が掲載されている。キャッシュフローをテーマにしたセミナーや研修も人気だそうだ。それもキャッシュフロー計算書が必要になる上場企業だけでなく、中小企業経営者もこぞってそういったセミナーに参加しているらしい。キャッシュフロー経営の本質を理解してくれているのなら良いのだが、またまた大企業の真似をして自己満足に陥る経営者を輩出しないことを願うばかりである。
株式を公開していない企業にキャッシュフロー計算書は必要ない。キャッシュフロー計算書はP/LとB/Sだけでは結果しか分からないため、どういうプロセス、どういう原因でキャッシュの増減が起こったのかをステークホルダーに伝えるためにある。非公開企業で、ましてや中小のオーナー企業でわざわざそんなものを作ることに何の意味があるのか。資金繰りと結局同じ事である。資金繰りというと経理担当者の仕事で、キャッシュフロー経営というと何か高尚な感じがして経営者の出番であると考えるのだろうか。キャッシュフロー経営とはキャッシュフロー計算書を作ることではなく、経営効率を上げ、収益性を高めていくことであり、別段新しいことではないのだ。少し財務のことが分かっている経営者なら、とっくに考えていたことであり、今までそういうことを考えていなかったという経営者が余程どうかしているのだ。京セラの稲盛会長の「実学」を読めば分かるように、計算書があるかないかに関係なく、キャッシュの動きをつかんで経営することは当然のことである。一連のキャッシュフロー本と稲盛氏の実学の違いは大きい。理論理屈でキャッシュフローを考えるのではなく、経営の現場で金の動きを捉えることだ。中小企業でわざわざ他人にキャッシュの動きを教える必要などないのだ。今ごろ、「やはり経営はキャッシュが大切だ」と考えているような流行に敏感な経営者に言いたい。まずは基本を知ってから流行を追え、と。
とはいえ、企業経営者がキャッシュフローに関心を持つことは歓迎したい。右肩上がりで市場が大きくなり、購入した物が確実に値上がりする時代ではない。借金も資産のうちだと、銀行に甘えていられる時代でもない。我々はいざと言う時、債権放棄してもらえる企業ではないのだ。キャッシュフロー経営が一時の流行りで終わらないことを切に願う。
1999年3月
インターンシップ
大学生のインターンシップが増えつつある。在学中に企業での実務経験を積むというものだ。その中で自分に合った仕事を探したり、企業側も実際に仕事をさせてみて人材を選別できる。しかし就職協定にそった一律採用を続けてきた日本企業にはまだ受け入れの体制が整っていない。インターンシップのコーディネートを行う株式会社キャリアビジョン(東京都中央区八丁堀、吉田理宏社長)では、この3月に3日間のインターンシップフェアを行う。すでにインターネットを通じて1000名を超える学生の応募があるそうだ。学生たちは社会に出る予行演習としてインターンシップを積極的に行いたいと考えている。しかし企業側ではその受け入れが大変だ。一括採用では人事部がすべての手続きや選考を行っていたが、インターンシップで現場の仕事を体験するとなれば、それぞれの部署で学生の教育や面倒を見なければならない。人事部としても優秀な学生を選考するためにインターンシップを活用したいわけだが、現場の抵抗がある。忙しいのに学生の相手をしていられないというわけだ。これがインターンシップフェアが3日間である理由だそうだ。本当は3日では足りないのだが、企業現場での受け入れを考えると3日くらいが限度ではないかという判断だ。もちろん今後は長期のインターンシップもコーディネートしていく計画である。
今年は日本のインターンシップ元年と言ってもいい年になるだろう。今年はまだ本格的な動きではないものの、これから確実に増えてくることは間違いない。とすると必然的に企業の人事に対する考え方も変えて行かなければならない。人事は採用の手続きやコーディネートを行い、入社後の手続きや給与計算などを行う。その他の採用選考や配置、評価、教育などは各部署、もしくは各事業部やチーム、小集団に任されるようになる。ゼネラリスト育成からスペシャリストの活用へと人事政策も変わってくるだろう。何も知らない真っ白な新卒新入社員が毎年入り、それを一から教育して、いろいろな仕事を経験させながら幹部候補として育てていくという一律的な人事ではなく、すでに一定の職務能力を持ちスペシャリストとして入社する新人や他社での経験を持つ中途入社組、定年退職後のキャリアを活用する中高年活用など多様な人事を実現していく必要がある。
すでに、2000年4月入社の新卒採用はスタートしている。自社の採用はどうあるべきか、今後の人事政策をどのようにするべきかを考えながら取り組んでいただきたい。ちなみに我がNIコンサルティングでもインターンシップを受け入れる計画である。
1999年2月
経営の道標 年度別
経営の道標 2024年版
経営の道標 2023年版
経営の道標 2022年版
経営の道標 2021年版
経営の道標 2020年版
経営の道標 2019年版
経営の道標 2018年版
経営の道標 2017年版
経営の道標 2016年版
経営の道標 2015年版
経営の道標 2014年版
経営の道標 2013年版
経営の道標 2012年版
経営の道標 2011年版
経営の道標 2010年版
経営の道標 2009年版
経営の道標 2008年版
経営の道標 2007年版
経営の道標 2006年版
経営の道標 2005年版
経営の道標 2004年版
経営の道標 2003年版
経営の道標 2002年版
経営の道標 2001年版
経営の道標 2000年版
経営の道標 1999年版
経営の道標 1998年版
NIコンサルティングへの
お問い合わせ・資料請求