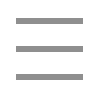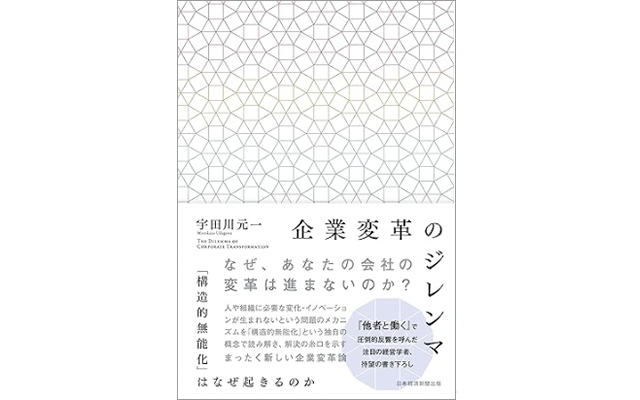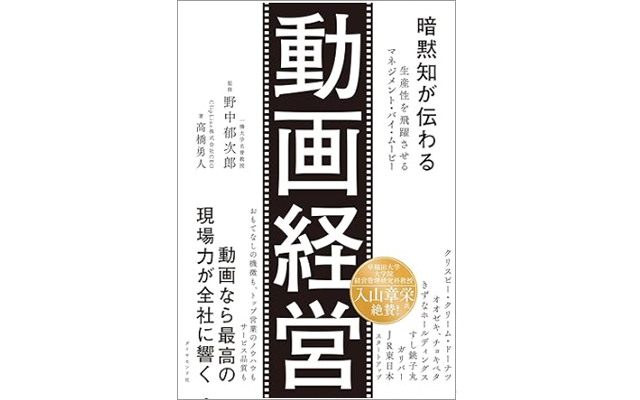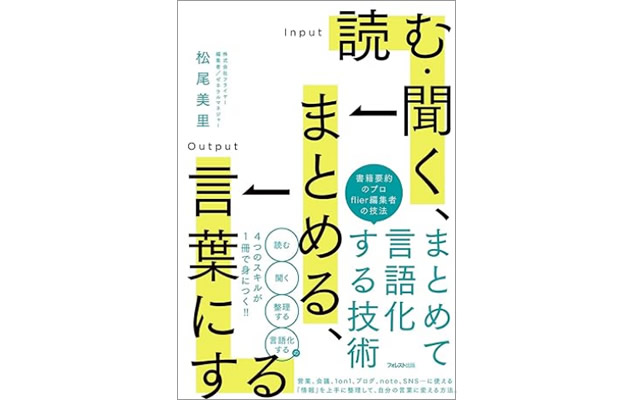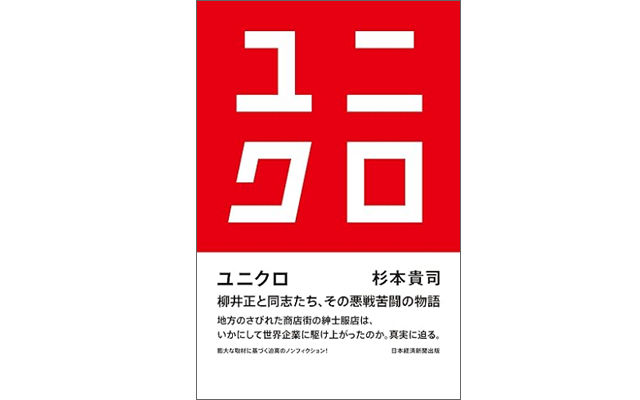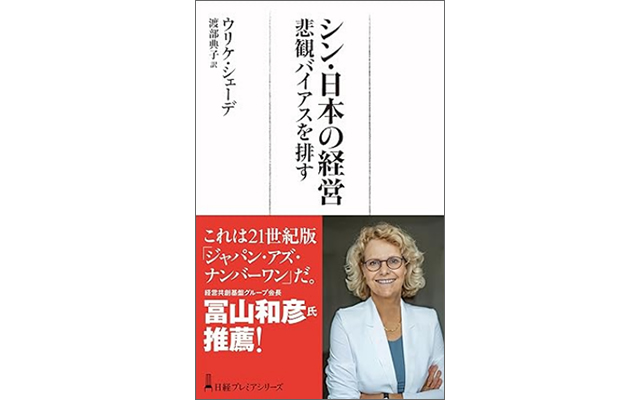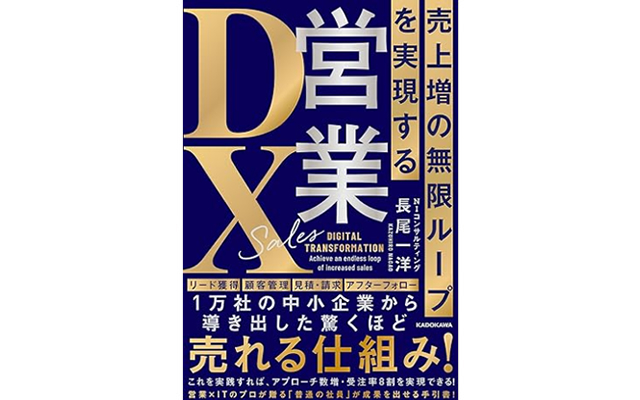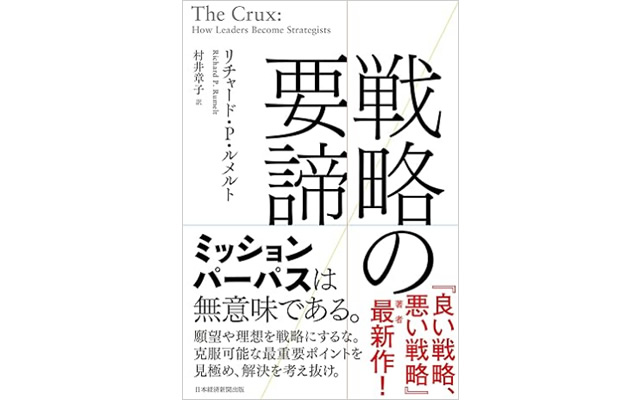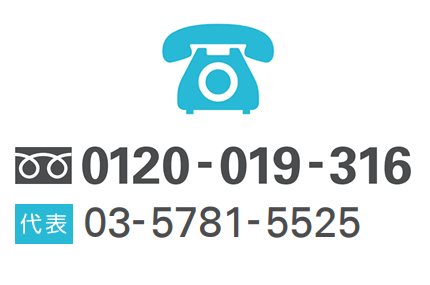企業変革のジレンマ 「構造的無能化」はなぜ起きるのか
埼玉大学経済経営系大学院准教授による経営改革本。結構売れているみたいだし、「構造的無能化」というワードに引き寄せられて読んでみたのだが、JTC(Japanese Traditional Company)向けのエッセイ集のように感じた。企業変革と言葉で言うのは簡単だが、JTCを変革させるのはかなり難しいだろう。その難題に対して解決策を提示するチャレンジは素晴らしい。
本書では、その難しい企業変革を成し遂げるには、組織の「多義性」を理解し、組織の「複雑性」に挑み、組織の「自発性」を育めと説く。言葉はそれっぽいが、そんなことはJTCにお勤めのご当人たちがよく分かっているのではないかと思う。分かっているけど出来ないから困っているのであって、それを他人事のように評論されても解決策は見えてこない。
問題を論うばかりで解決策がないなぁ~と思いつつも読み進め、最終の第8章「企業変革を推進し、支援する」に到達。いよいよ具体的な策が出て来るか!?と期待したのだが、「本社のコーポレート機能の1つとして特命組織を作って、経営陣が『全社戦略を考えられるようになる』ようにファシリテートして、各役員が自分の役割をしっかりと理解し、実行できるようになるまで支援せよ」と来た。こんな呑気なことを言っているからJTCの変革が進まないのだろうなと思う。
そもそも全社戦略も考えられず、担当部署の役割も理解できないような役員は解任して、戦略立案できない人をできるように支援していくだけの力量のある人材が社内にいるなら、その人をトップに抜擢せよ。そうしたらすぐに企業変革できるよ、と思った。では、なぜこの本をおすすめBOOKSに取り上げているのか?ということになるのだが、どうも売れているようなので、日本企業の99.7%を占める中小企業の皆さんはこの本を参考にしてはダメですよという情報提供である。もちろん、反面教師という役割もあるわけで、本書を読んで「こんな経営をしていては大企業病になるだろうな」と学べるという点ではおすすめできる。興味のある方はご一読を。