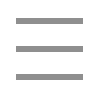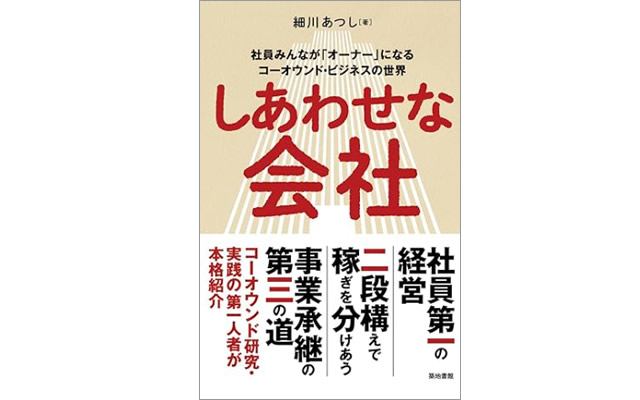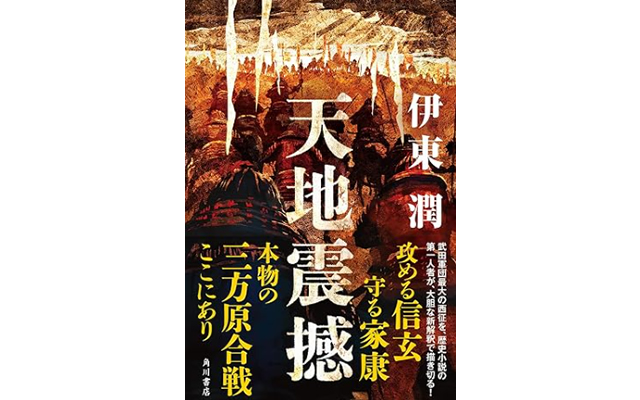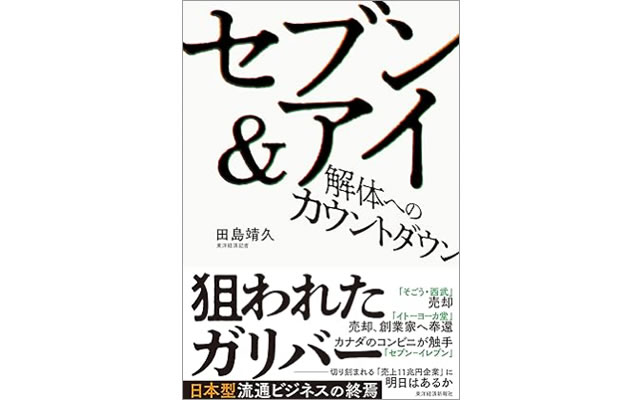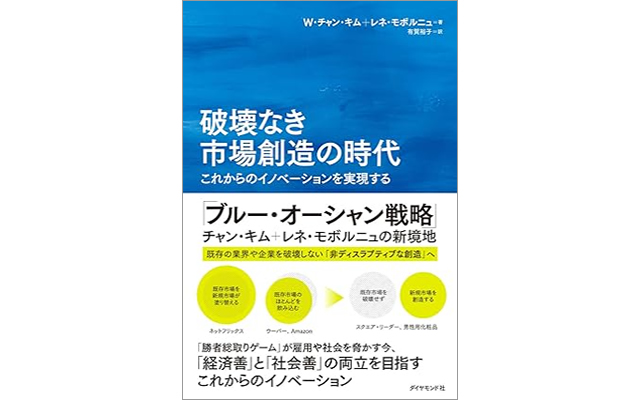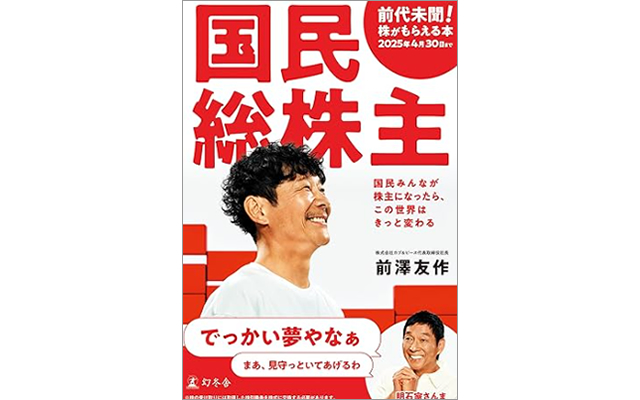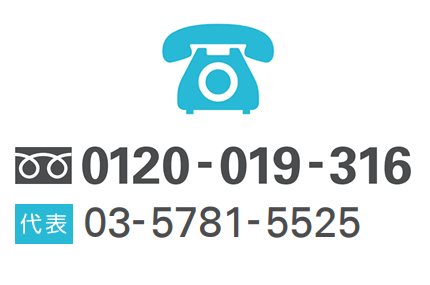しあわせな会社
従業員が大株主となる経営、「コーオウンド・ビジネス」の解説書。サブタイトルは、「社員みんなが『オーナー』になるコーオウンド・ビジネスの世界」。本書は、2025年に出たばかりの本だが、実は2015年に出版された「コーオウンド・ビジネス-従業員が所有する会社」の増補改訂版だった。10年間で増えた日本企業の事例が追加で記載されているようだ。
著者は、一般社団法人従業員所有事業協会代表理事、株式会社コア・ドライビング・フォース代表取締役で、跡見学園女子大学マネジメント学部・大学院マネジメント研究科の教授、立教大学大学院社会デザイン研究科客員の教授も務められている。
私は「従業員共有型経営」と呼んでいるのだが、内容的にはほぼ同じ主張、提言をされている方がいて良かった。大学でも教えておられるようだし協会も作られているみたいなので、是非この考えを広めていただきたい。ただ、考え方に賛同する私ですら前著を存じ上げなかったし(今回の本はたまたま日経の広告で見つけた)、「コーオウンド」という言葉が日本では分かりにくいように感じる。英語圏でも、「エンプロイー・オウンド」「エンプロイー・オーナーシップ」など名称にバラつきがあると思う。そして、本書では「コーオウンド・ビジネス」を「従業員所有事業」と日本語訳されているが、「コーオウンド」と言うなら「共有」の方がいいと思う。
ちなみに、私は本書の著者、細川先生と張り合いたいわけではなく、協力協働したいくらいだが、パクリ(物真似・受け売り)だと思われるのはイヤなので、2008年に出した「すべての『見える化』で会社は変わる」(実務教育出版)という本の中で「社員株主会社」という提言をしていたことをお伝えしておく。その後、レベッカ・ヘンダーソンの「資本主義の再構築」という本が2018年に出て、「従業員所有型企業」(原著を確認していないがエンプロイー・オウンド・ビジネスを訳していると思われる)という提言を見つけ、「社員株主会社」では分かりにくいし、なんだかダサいなと思って「従業員所有型経営」と呼び方を変えていたのだが、これだと現オーナー(社長)に誤解を与えそうだと思って最近は「従業員共有型経営」と呼んでいる。どう呼ぼうと中身は同じようなことなのでどっちでもいいような話だが、大切なことはそれを実践する人(企業)が増えることなので、パッと読んで理解しやすい名称の方が良いと思う。ということで、日本では「コーオウンド」をパッと理解する人が少ない気がするので、「従業員共有型経営」と呼ぶことを推奨したい。
本書では、「完全コーオウンド」「100%コーオウンド」と言って、100%従業員所有にすることを目指している感じがあるが、それには抵抗感のある企業オーナーが多いと思うので、30%から49%くらいのシェアで従業員が株を所有するという形が一番馴染みやすいのではないかと思う。
いずれにせよ、こういう経営もあるなという発見や気づきがあると思うので、是非本書を読んでみていただきたい。