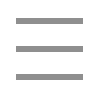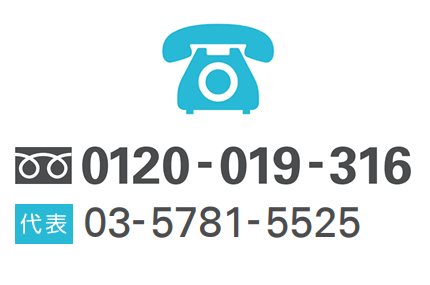代表長尾が語る経営の道標
2ヶ月に一度更新しています
2026年版 経営の道標
2026年 丙午(ひのえ うま)
昨年に続き、年初からトランプの動きに世界中が振り回されている。ベネズエラへの奇襲と大統領夫妻の拘束はまるで映画のシーンのようだったし、グリーンランドの領有を主張し、西半球を牛耳る「ドンロー主義」を訴えたのにも驚かされた。さらには、利下げを要求して批判を続けていたFRB議長に対して刑事捜査を始めたりと、もはや法も秩序もおかまいなしの暴れっぷりだ。
日本国内では高市首相による衆院解散総選挙。予算成立を後回しにして解散・・・。と思ったら、公明党と立憲民主党が一緒になって中道改革連合という新党を作ると言う。政治信条や政策は後回しのようだが、そもそも与野党が揃って消費税減税という選挙対策最優先の公約を掲げていて、政策論議にもならないポピュリズムが露呈している。
それを見て、日本国債の長期金利は跳ね上がり、世界は日本にNOを突き付けている。インフレ対策が必要だと言いながら実質金利はマイナスのままにして、巨額の債務残高があるのに積極財政を訴え消費税減税を進めるという矛盾したことばかりしていては、さすがに日本への信認も棄損して当然だろう。
という何とも困った状態で、丙午(ひのえ うま)を迎えようとしている。
十干の丙は、「陽」や「火」を意味し「炎のように燃え広がる火」を表している。「大地から芽が出て葉が広がった状態」という意味もあり活力やエネルギーを象徴する。
十二支の午は、南の方角や太陽が1番高く昇る正午を象徴し、「真夏の火(陽・日)」や「勢いや運気が最高潮に達している状態」を表す。馬から連想される「スピード」や「勢い」もあるとされる。
ということで丙午は、火の力が重なる干支とされ、勢いの強さや激しさ、情熱を象徴し、かつては「力が強過ぎて制御できない」「丙午の年は火災が多い」などと考えられ、不吉な年ともされた。今や迷信のようなことを考える必要もないだろうが、立春の2月4日から丙午が始まる前にいろいろと懸念材料があるから、ちょっとしたことが行き過ぎ、暴走し、大事にならないようには気を付けておきたい。
丙午ということで気を付けたいのはやはり「火」だ。山火事も頻発し長期化しているが、火事には気を付けたい。特に大地震に伴う火事。そして、企業経営の道標としては、自社の経営を「火」の車にしないこと。インフレで諸経費が高騰し、原材料なども騰がっているところに、人件費増が来て、値上げが思うようにできない会社はかなり経営がきつくなると思う。借入依存度が高くて利益もカツカツなら金利上昇もじわじわと効いて来るだろう。
約30年続いたデフレに慣れ過ぎて、「まぁ前年並みでいいだろう」という緩い経営者が増えているようにも思う。これではいけない。また、「値上げなんてしたら客離れするから怖くてできない」という思い込みも強固だ。そして顧客も30年のデフレに慣れているから、値上げに対する嫌悪感が強い。だからと言って、値上げはできないと諦めてしまったらそこで試合終了。インフレには対応できないことになる。
まだ金利は実質マイナスだし、インフレ率も3%程度なのだから、今のうちに手を打っておくべきだ。金利がさらに上がり、インフレが加速したりしたら手の打ちようがなくなる。すでに新卒の初任給はかなり上がって来ているし、最低賃金も秋にはさらに5%程度上げて来るだろう。デフレ時代には待っていれば何とかなったが、インフレ時代には、待っていてはさらに高くなり損をすることになる。先手必勝。なるべく早く手を打つことが必要だ。必要な資金も早めに借りておこう。インフレは借入負担を軽くしてくれる。
値上げをし、利益を確保するための考え方は、2024年7月の経営の道標「加工錬成度を上げよう」で「利益創出方程式」を解説しているのでそちらを参考にしてもらいたい。
多少余裕のある会社は、インフレヘッジで金(Gold)の購入をしておくことをおすすめする。金(Gold)については、2025年9月の経営の道標「通貨の信用低下に備えよ」でも指摘しているので参考にしてもらいたい。わずか4カ月前に書いたことだが、そこでは金(Gold)の価格が、1トロイオンスあたり3600ドルを超え3700ドルに迫っていて、日本国内でも、1グラムあたり19000円を突破したと書いている。今(2026年1月)はどうか。
NYでは、1トロイオンス5000ドルに迫り、日本では1グラム28000円に迫っている。たった4カ月で、NYは35%、日本は47%上昇。ドル-円の為替変動があるから、細かい数字は気にする必要はないが、要するにそれだけ通貨の価値が下がっているということ。金(Gold)が騰がっているのではなく通貨が下がっているのだ。現金の円を持っているだけではこの事態を乗り切ることはできない。
金(Gold)は配当もないし、金利がつくわけでもないから、過剰投資してもいけないが、イザという時のために現金相当額の2割から3割は持っていても良いと思う。もし、通貨暴落、ドル基軸体制の崩壊といった危機が来ればさらに金(Gold)は暴騰して貴社を救ってくれるだろう。何も起こらなかったり、金(Gold)が多少下がったりしても、それはそれで現金の価値が上がっているから、保険としては悪くない。危機に備える以上は、現物で持つ方がいいが、火事に備えてそれなりの耐火金庫に入れておこう。
トランプ大統領が11月の中間選挙まではどんなことをしても好景気、株高を演出するかもしれないが、それ以降が結構危ないと思う。相場の格言に、「辰巳天井」「午尻下がり」というものがある。巳年の昨年は史上最高値ラッシュだった。まさに天井。2026年、午年は後半にかけて尻下がりとなるというのが統計的な格言。馬の勢いが止まった時、何が起こるかをよく考え、その時に備えて準備をしておくべき年。それが丙午である。
2026年1月
経営の道標 年度別
経営の道標 2024年版
経営の道標 2023年版
経営の道標 2022年版
経営の道標 2021年版
経営の道標 2020年版
経営の道標 2019年版
経営の道標 2018年版
経営の道標 2017年版
経営の道標 2016年版
経営の道標 2015年版
経営の道標 2014年版
経営の道標 2013年版
経営の道標 2012年版
経営の道標 2011年版
経営の道標 2010年版
経営の道標 2009年版
経営の道標 2008年版
経営の道標 2007年版
経営の道標 2006年版
経営の道標 2005年版
経営の道標 2004年版
経営の道標 2003年版
経営の道標 2002年版
経営の道標 2001年版
経営の道標 2000年版
経営の道標 1999年版
経営の道標 1998年版
NIコンサルティングへの
お問い合わせ・資料請求